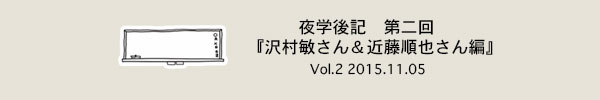先日、『映画夜学』第二回を催しました。
ゲストは……、
東京テアトル株式会社で番組編成をご担当されている沢村敏さん。
そして、日本出版販売株式会社にて映像制作をされている、元シアターNの支配人でもあった近藤順也さん。
お二人とも、長年「興行」に携われてきた方々です。
夜学の参加者は、映画監督からラインプロデューサー、助監督や脚本家など、映画の作り手たちです。
本来、映画製作とは企画の立ち上げに始まり、劇場公開、更にはソフト化までを視野に入れるもの。ただ、いわゆる作り手の多くは、お客様へ届ける『興行』というプロセスに疎い傾向があるのではないでしょうか。というか、ほとんど『興行』という現場で何が行われているかを知らないのが実情です。
そこで、今回の『夜学』のテーマは、あらためて『興行』の現場を捉えなおそうというものでした。
東京テアトルで『番組編成』を担当している沢村さん。「番組編成は、不利になるので、なかなかこういう場に出てこないのですが……」とのこと。
仕事柄、作り手たちとは作品ごとに付き合わねばならず、情に流されてはいけないという自戒も込めて距離を置かねばならないのだと思います。
ところで、「番組編成」という言葉は聞きなれないものではないでしょうか。
おおざっぱに言えば劇場にかける映画を編成する立場のこと。公開する映画を選んでいるわけですね。沢村さん、近藤さんのお話しを伺っていますと、公開する映画を選ぶだけの確かな審美眼がおありだと感じました。ただ、作り手にその源泉を悟られれば、いざという時に、ことわりづらくなるかもしれません、がゆえに、沢村さんは、「番組編成の担当者で前に出てくる人はあまりいないはず」だといいます。
それだけに、沢村さんや近藤さんといった映画を「選ぶ」方々と胸襟を開いて討議できるのは貴重だったといえるかもしれません。
「選ぶ」と書くと、何か語弊が生じそうな気もします。僕はこう表現してもいいかもしれないと思います。お二人は、もしかしたら映画とお客さんをつなぐキュレーター的立場を担っているのかもしれないと。
お二人はその膨大な「興行」の経験から、どんな映画をどんなタイミングでお客さんにどのように体験してもらうかを、日夜導き出しています。
映画産業における複雑なお金の流れや産業全体の売り上げ規模、あえて映画をメジャーと単館系という二項対立に見立てたうえで今後の日本映画産業の行く末についてなどなど、沢村さん、近藤さんのお二人は、ご自分の経験を踏まえながら、普段公にできないようなお話しまで、参加者に聞かせてくださいました。
何をして『単館系』かという定義は、実は曖昧なのですが、それはひとまず置いておいて、いわゆるパブリックイメージとしての『単館系』映画の現在の売り上げは、日本における映画産業全体の5パーセントほどだそうです。
ところで、かつてミニシアターブームという流れがありました。だいたい90年代から00年代にかけてのことだと思われます。そのころの『単館系』の売り上げは、全体の12パーセントくらいはあったといいます。
なぜ規模が縮小したのかという理由はわかりません、しかし、現実として、単館系映画苦境の時代であることには間違いがありません。アート映画は黙殺され、無名キャストではお客が入らない、お客を入れるためにネットでバズらせる、結局みんなが見る映画が売れる、そんな時代であることはたしかです。
そんな中、シニア層は比較的「ミニシアター」を訪れるといわれています。そこで、シニア層の年齢、つまり60歳前後を起点に考えれば、ミニシアターブーム真っ只中の30年前、彼らは30歳代だったいう事実が浮かび上がります。つまり、現在のシニア層が、ミニシアターブームのコア層だったのだという仮説が成り立ちます。
「単館系」の分厚い客層はミニシアターブームを支えた現在のシニア層、しかし、今先ほどの「5パーセント」という厳しい現実を考えれば、シニアだけでなく、新入生を招き入れることが急務ですが、なかなか入ってきてくれていないことが現状です。
暗澹たる気分になるばかりかというと、しかしそうでもないのでは?と近藤さんは言います。
ミニシアターブーム当時、その震源地は渋谷だったそうです。そんな渋谷地区で、近藤さんは、13年間、その隆盛と収束を目の当たりにしてきました。ブームが去ったきっかけは、渋谷パンテオンという大劇場がなくなったことだと近藤さんは分析します。
「最初に見る映画が単館系という人は少ない、ブームを支えた現在のシニア層の方々も映画の原体験は大劇場だったはず。そこで見たメジャー映画をきっかけに映画が好きになり、徐々に単館系へと食指を伸ばしていったのでは?」と近藤さん。
言われてみれば確かに僕らもそうでした。
そういう意味では、現在の映画の本拠地は、新宿エリアでしょう。巨大なシネコンが多数あり、かつミニシアターも揃っています。
沢村さんがいらっしゃるテアトル新宿は、中でも邦画の聖地的位置づけだと思います。
沢村さんも、「2014年くらいから、お客さんは戻りつつあるのかなという印象がある」と語ってくださいました。
シネコンでメジャー映画ばかりがかかる状態の中では、結果としてメジャー映画だけに飽き足らない人々から単館系映画も求められるといいます。
「そういう人に向けて、単館系はがんばるべきだと思う。それはテアトルだけが頑張ってもだめで、今は、新宿エリアに限らず、劇場がそれぞれの個性を出して頑張る時かなと思う」と、沢村さん。
更に沢村さんは続けます。
「成熟した映画社会の理想的な形態は、選択肢があること。多様性がなければ意味がない。自分が見たいと思える映画を選べる状態が理想的だし、作品数を見ていけば自分の好きな映画がわかってくるはず。その中で、いわゆる『単館系』のパーセンテージを15パーセントまでは回復させたいと考えている」
特にこの言葉の冒頭、「成熟した映画社会の理想は選択肢があること」については、思わず首肯してしまいます。
ただ、選択肢を維持するためには、もっとお客さんたちに映画を観る機会を増やしてもらわねばなりません。
どうすれば劇場にもっと脚を運んでもらえるかを考えるとき、結局、「教育」に行き着くのではないかと、討議しながら、僕らは結論を得ました。
「映画を観ることはまさに体験、必ず行為が伴うもの。例えば、両親に連れていってもらった幼少期の体験など。そんな経験をすることで、のちに劇場に足を運ぶ機会が増えていくのでは? そのために我々は映画体験をいかに提供するかを考えなきゃならない」という沢村さんのまさに正鵠を得た言葉が印象的でした。
今回の『夜学』を通して、お客さんと直接結びつく沢村さんや近藤さんなど『興行』の方たちが、いかに映画体験を提供するかを考え続けていることがわかりました。
そして、お二人のおかげで、作り手である僕たちの中に、作家性の醸成と共に観客たちへ映画体験を届けるという意識が芽生えたことが、なによりもの収穫だったように思います。
冒頭、「あまり前に出ることはない」という言葉があったにも関わらず、我々のお声がけに、快く登壇していただいた近藤さん、沢村さんに、感謝しつつ、また改めて、この「映画夜学」で、興行論を展開させられたらなどと考えている次第です。
(いながき きよたか)