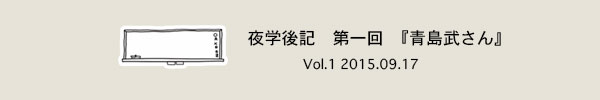思うに、現場の声が、後世に残ることはありません。
もちろん、メイキングなどで、「偶発的に」残ることはあるかも
しれませんが、原則的にはフローしていきます。
反対に、ストックを目的として記録されるものには、ある種の規
範的な力が働きます。いつ、どこで、誰に参照されても隙がない
ように、編集し、まとめられます。
『現場の声』には、そういった力は働いていません。もし、規範
的であろうとすれば、「現場」にとってマイナスになることさえ
あると思います。それだけに、『現場の声』は生の声だとも言え
ます。
どうして、こんな原則的な話から始めるかというと、この「映画
夜学」という催しで話される声も、基本的には、現場の声=生の
声だからです。
フローしていく言葉の効果は、きわめて、短期的です。まさにそ
の瞬間に対する収拾・解決が目的ですから、体系化したりする意
味はあまりありません。殊更、フローしていく言葉を、文脈を無
視して拾い上げて、論うこと(たとえば、炎上)にも、意味があ
りません。
ただ、この現場の声=生の声=フローしていく言葉が、まったく
後学のために役に立たないかというと、そうではありません。
記録に対しては、意味がないが、記憶にとどまり、個々人の中で
醸成して、経験則や、知恵につながるのではないかと、僕は考え
ています。
例えば、師匠-弟子の関係における、師匠の言葉のように。
さて、ここで「映画夜学」そのものについて、ご説明しなければ
なりません。
そもそも「映画夜学」とは、隔月に一度、映画(のみならず、映
像全般)にかかわってこられた先輩をお呼びして、後輩たちが話
を聞くという会です。
なぜこのような会を催そうと思い立ったかというと、それは、と
ある晩のことです。
僕は、映画『ソレダケ/that’s it』でご一緒させていただいた大崎
プロデューサーとお酒をご一緒していました。
お話も極まり、ふと僕は大崎さんがいかにして映画業界に入られ、
どのような経験をしてきたか、聞いてみたくなったのでした。
僕の無理なお願いに、大崎さんは、訥々と語ってくれました。そ
して、それは、とても面白いものでした。同時に、ためにもなり
ました。彼が最前線で活動していた80年代から90年代、僕がま
だ学生でただの映画ファンだった時代、映画界がどのような雰囲
気だったのか、僕は大崎さんの話によって、実感できたかのよう
に思いました。
さて、現在の映画界は、横のつながりが弱いと言われています。
若い作り手たちは、それこそ散逸的・ゲリラ的に映画を作り続け
ています。文字通り『発明』に迫られながら対応しているのです
が、そこに日本映画の系譜につながるような智慧があれば、と思
う局面が少なくありません。ということは、つまり、僕たちは、
実は横のつながりが弱いのではなく、縦のつながりが弱いのでは
ないか、これが、かねがね僕が思っていたことです。
撮影所システムがなくなって久しく、かつて上から下へと伝えら
れていた知識、知恵、伝統=まさに生の声の伝承が、今は断絶し
ている感があります。
ならば、伝承の回路を作ればいいのではないか……、そういうわ
けで、「映画夜学」という会に結実しました。
さて、先日、「映画夜学」第一回を催しました。ゲストにお越し
いただいたのは、青島武さんです。ここで、その模様に少し触れ
たいと思います。
詳細なレポートというより、いながきが個人的に感じた事を中心
に書きたいと思います。
青島武さんのプロフィール:
青島さんには、映画との出会いに始まり、どのようにキャリアを
積み重ねたかをお話しいただき、そして、後半に至り、日本映画
の情況について、無礼講的に参加者たちと意見を交わしていただ
きました。
本当にありがとうございました。
挨拶の始めに、青島さんは自らを称して、「僕は、失言してしま
うタイプなので……」とおっしゃっておりましたが、まさに、
『映画夜学』は、前述のような生の声を聞くことができる会を目
指すゆえに、そういったその場でしか聞くことが出来ない言葉は、
願ったり叶ったりでした。
事実、青島さんは、後輩たちの前で、ご自身の経験を、あえてオ
ブラートに包まず、ストレートに語ってくださいました。これこ
そ、「映画夜学」の醍醐味であり、今後に先鞭をつけていただい
た感さえあります。
それゆえに、ここにそのすべてを紹介できず、というよりも、ほ
とんどが文字として残すこと能わない内容ですので、できれば、
記憶を頼りに、そのさわりだけでもお伝えできればと思います。
さて、青島武さんは、現在、脚本家として活躍されています。
有名作・大作の中でも特に気骨のある作品を多く書かれておりま
すが、青島さんは、そのキャリアを脚本家としてスタートさせた
わけではありませんでした。
日本映画学校の前身である横浜放送映画専門学院の六期生として
卒業した後、東宝撮影所内の会社の契約制作部となったことが青
島さんのキャリアのスタートだったのです。
その後、あまたの変遷を経て、いち早くプロデューサーとなった
青島さんは、高橋伴明監督作、哀川翔主演の「とられてたまるか!
」シリーズで、初めて脚本家としてクレジットされることになる
のですが、制作部からプロデューサーへと仕事をしていく中に、
すでにシナリオライターへの準備が隠されていたようです。
そんなお話の中で、僕にとって特に印象深かったのは、プロデュ
ーサーとして活動していた青島さんが、シナリオをどのようにし
て自分のものにしていったか、というお話でした。
そのころのシナリオ原稿というと、まだ手書きが多く、直接作家
さんから生原稿をもらいうけ、コピーを取ってから印刷所に入稿
していたといいます。
そして、この生原稿のやりとりを行うのはもっぱら制作部さんの
仕事。しかも、とりわけ制作進行の仕事だったそうです。
将来、脚本家になるにしろならないにしろ、まだ駆け出しのスタ
ッフが、脚本家の先生と直に接し、あまつさえ生原稿に触れるこ
とは、今では考えられないことで、僕たちの世代にとっては、と
ても幸福なこととして感じられます。
と言うのも、こういった生身の経験というものは、学校で教わる
より何倍もの勉強になるからです。
ある作品で、23歳だった青島さんも、とある高名な脚本家さん
の生原稿をとりに行ったそうです。
喫茶店で生原稿を受け取ると、その足で文房具店へ、今のように
コピー機がコンビニにない時代です、しかもやたらと時間がかか
ります。待っている間、何をするかと言えば、複製が仕上がる間
に、やはり読んでしまいます。
コピーを終え戻ると、先生は、開口一番「どうだ?」と青島さん
に問いかけたといいます。もちろん何も考えず青島さんは「よか
った」と答えるのですが、先生は「どこがよかった?」と忌憚の
ない意見を求めたといいます。大作家と23歳の駆け出しのシナ
リオをめぐる意見の交換が、こんな原稿の受け渡しをめぐって、
やりとりされたことを考えると、今よりよほど映画的感覚が鍛え
られたことだろうと、僕は嫉妬してしまいました。
また後年、プロデューサーとなり、高橋伴明監督と仕事をご一緒
する機会が増えた青島さんは、そのころ伴明作品をお書きになっ
ていた西岡琢也さんの原稿もよく受け取りにいったといいます。
やはり手書き原稿にはクセがあるそうで、印刷所でも作家ごとに
原稿を読める人が決まっていたという逸話も残っているそうです
が、青島さんは、この西岡先生の原稿を必死に読むうちに、ほぼ
完ぺきに読みこなせるようになったといいます。同時に、真剣に
原稿に向かい合うことで、シナリオの内容がより頭に入ってくる
のでした。
これが、青島さん流のシナリオ修業というわけです。座学より実
地、僕は大いに首肯する部分があり、これに勝る修行はないと思
います。
そんなわけで、青島さんは、西岡先生に直接学んだという経験は
ないものの、生原稿の受け渡しが縁で、西岡先生公認の弟子なの
だそうです。
こういう経験を持てることは、僕らの世代の誰もが歯噛みするほ
ど羨ましいものではないでしょうか。
このほか、特に記憶に残ったことに、「青島流企画書の書き方」
というものがありました。
同時代のプロデューサーたちは、日夜企画書に腐心していると思
いますし、なかなかその企画が通らないのも実情です。もちろん
企画が通らないのは、時代のせいもあるかもしれません。しかし、
企画書の良しあしに原因があるのではないかと考えるのも人情で
す。
翻って、青島さんは、プロデューサー時代、いくつもの企画書を
仕上げ、成立させてきました。
その「企画書のツボ」のようなものを、たくさん聞くことが出来
ましたが、なかなかここで詳らかにできないことが残念です。
他にも、やがて会の後半、ざっくばらんに参加者たちの意見も飛
び交うようになってから、「日本映画」という、ともすれば夜郎
自大なテーマを僕らが話し出すと、青島さんは控えめにもこんな
ことをおっしゃっていました。
今の日本の映画界に、困難さが多いということを踏まえ、「その
困難さを招いたのは、あなたたち先輩じゃないですかと、僕たち
は言われても仕方がない。だから、逆に、今、そして今後をどう
思っているのか、君たちの本音を聞かせてほしい」と。
今後をどうしていくかということについては、僕はまだわかりま
せんが、一つ、大きなキャリアを積まれてもなお、こうした謙虚
な姿勢を持つということが、なにより僕は勉強になったような気
がします。
やがて「夜学」は「夜会」となり、話は様々な話題に及びながら
幕を閉じました。
さて、「映画夜学」では、こんな門外不出と言ったら大袈裟です
が、テキストに残らない声を集め、先輩から後輩へと、伝えてい
くことを目的としています。
すでに第二回の「先輩」も決まっています。今後も、ぜひ、先輩
方の知恵と経験を引き出せる会にしていけたらと考えております。
(いながき きよたか)