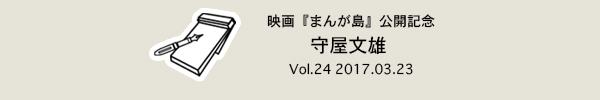第一回
縁あって、守屋文雄監督「まんが島」を試写で拝見しました。
そうしたら、どうしても監督本人のお話しを聞いてみたくなりました。
つてを頼りに、お願いすると快く受けてくださいました。
実際お会いしてみると、お話しは尽きず、ついつい時間を忘れてしまいました。
とにかく、お読みください。
そして、「まんが島」を観てみてください。
(文責:いながききよたか)
profile:
守屋文雄(もりやふみお 1976年生)
2001年、日本大学芸術学部映画学科卒業。
2005年、「ヒモのひろし」が第二回ピンク映画シナリオ募集に入選。
その後、脚本家、俳優、監督として活動。
2012年、映画「キツツキと雨」(沖田修一監督)、2016年ドラマ「ディアスポリス 異邦警察」などの脚本作品がある。
2017年㋂、満を持して監督作品「まんが島」公開。
・「ずっと撮らなければという思いはあった」
いながき:まず、始めに僕の雑感を話させてください。
「まんが島」を試写で拝見しました。本編が始まってすぐ、僕は驚きました。観終わって、僕としては単純に「おもしろかった」では片づけられない何かがあると思いました。ひさしぶりにすごいものを観たと感じたんです。
そしていろいろ考えさせられました。
普段、守屋監督が脚本を書いているということも知りました。
僕は普段シナリオを書いている身として、作劇そのものを呪縛に感じている部分があります。「まんが島」にはその作劇を内側からメキメキと解き放った爽快感を感じたし、加えてそもそも映画を人に見せるとはどういうことなのか、ということも考えました。
失礼ながら、決して誰もが楽しいという類の映画ではないかもしれません。それでいて「まんが島」は、まぎれもなく「映画」です。「まんが島」は僕に、もう一度映画について、考えさせたわけです。
そもそも「まんが島」を作るに至った経緯はどういうものだったんでしょうか。
守屋:ありがとうございます。
「まんが島」撮影は2013年の夏です。もうそろそろ丸四年になりますね。
ずっと撮らなきゃなという思いはありました。
2000年くらいに大学を出たんですけど、2007年、2008年辺りには、周りにいた自主映画の仲間たちが商業映画を一本なり二本なり撮り始めていて、自分もそうなるつもりで大学を出たし、やっていたつもりだったんですけど、その最初の一手目になるはずの作品をずっとやれていないと感じていました。
やっと周りがそういう状況になったことで尻に火が付いたところがあって、もういい加減、他の人の台本を手伝ったりとか、人の映画に出たりしているだけではダメだと思って、やっとそこで台本の準備をし始めたんです。
最初にいまある設定を考えたんですけど、でもこの内容ってやっぱり自主だと限界があるじゃないですか。それでも書き始めていたら、沖田(沖田修一監督)に「キツツキと雨」の脚本に誘ってもらって、そうしたら、ある程度まとまったお金が手に入るわけじゃないですか、そこで本当に作り出せると思ったんです。
最初から、どこかの会社に企画として持って行ってということは考えがなかったんですよね。自主映画として最初にみんなに見てもらえるもの、それは短いものではダメだと思っていて、長いもので作らなければと。
それまでやってきたことが、台本の仕事だとか、出演の仕事だとかだったので、やっぱりそっちがメインになっていく中で、合間を縫って台本を書いていたんですよね。
いながき:ということは、監督をしなければいけないとご自分では思ってるということですよね。
守屋:そうですね。
いながき:そもそもは日大の芸術学部なんですよね。
守屋:映画の監督コースを出ました。
いながき:僕らの世代って、同世代の映画人が多いですよね。日大だと、沖田さんもそうですし、
守屋:上に冨永さんがいて、下に入江君がいて、
いながき:大阪芸大の方では、山下さんや、脚本では向井さんとか。
守屋:ちょっと上では熊切さんですね。
いながき:ちょうど僕も脚本のデビューが2007年で、たしかにあの頃、周囲が世に出始めたころですよね。雰囲気はよくわかります。
守屋:そばにいる人が、急にあれよあれよと……。
いながき:そうですね。
・「ただ壊したい」
守屋:話を壊すみたいなことは考えていました。
仕事で頼まれるとどうしても渡せる台本にしなきゃいけないじゃないですか。そこにだんだん飽きてきたというか、そこだけに頑張る自分に、かなり限界を感じていました。
ただ壊したいと思って作ったんですが、意外と壊れてないなという気もしてるんですけど。
かといって、お話しのある他の映画がつまらないというわけでは決してなくて、それはそれでおしまいまで見るし、途中でがまんできなくなって途中で止めることはないんですよね。
いながき:「まんが島」という映画自体に壊す、壊れない、壊そうという意志の痕跡みたいなものがあって、僕はその部分が自分と変にリンクしてしまいました。そういう部分にアレルギーを感じる人ももちろんいるだろうけど、でも最近考えてみると、自分だけのものにしたいような映画って少ないと思います。石井監督の「爆裂都市」のような、「これはなんだ!」という、そういうニオイのする映画ってなかなかないですよね。そういう意味ではやってくれたと感じますね。
台本作りから、今ある完成した映画のイメージはあったんですか?
守屋:はい、それはもうあって、結果的にこうなってはいますが、それは目指した結果であって、こうなっちゃったということでは決してないんですよね。
いながき:書くプロセスはどんなものだったんですか。
守屋:最初は連載を勝ち取るという話で草稿を書いたんですけど、全然腑に落ちないというか、面白くないんですよね。それで、この映画のキャラクターたちがこの映画を見た時にたとえば笑ってくれるためにはどうしたらいいんだろうと、途中から考えるようになりました。島にいる状況だからこその映画の流れってあるよなと、どこかで方向転換したと思います。状況に導かれて、今の形の原型ができたというところはありますね。
台本はしつこく直してましたね。プロットみたいなものは作らなかったんじゃないかな。
いながき:たとえばいただいた仕事だったら、シノプシス(※)やプロット(※)というプロセスがあるじゃないですか。これは実は判子をもらう作業に似ていますよね。通過儀礼的に段階を踏まないと共同作業者が安心しないから、こんなものはどうでしょうと提案しながら前に進んでいく。プロットって半分はそういうもののためにあると思うんですよ。
逆に言えば、自分のためのプロットだったら全然違うものになるんですよ。
(※シノプシス:梗概、あらすじ)
(※プロット:おなじくあらすじと訳されるが、シノプシスよりもシナリオを意識して書かれる物語の筋)
守屋:そうですね。枚数もそんなに気にしなくてもいいですしね。
・「台本を読めばいい」
いながき:仕事ではなく、自分のためのシナリオって明らかに作り方が変わってくると思うんですよね。
普段お仕事ではどのような書き方をしていますか。
守屋:どうだろうな。A4の原稿用紙にハコ割るのかな……。100パーセント、ハコを割ってしまうと書けなくなるので、途中からもう最初のシーンから手で書いていきますね。
いながき:ハコ(※)を手で書くんですか?
(※ハコ:シナリオ内のシークエンスの塊、及びその配列。たとえば、大バコならば、起・承・転・結や序・破・急レベルのまとまり。中バコならば、オオバコを概ねそれぞれ四つか五つほどに割ったもの。小バコならばほぼシーン単一のことを指す)
守屋:手で書きますね、ある程度書いたらパソコンに打ち込むという感じです。
いや、もう、原作があってもなくてもいいんですけど、これは映画になりそうだというアイデアをプロットとして書かされることって、ものすごく殺されてる感じがしないですか?
いながき:しますね。
守屋:あれは本当になにをやらしてるんだろうって思います。
いながき:わかります。僕はやっぱり殺して書きますよ。
守屋:ネタ帳みたいなものに、ちょこちょこっと書いたセリフのやりとりをとっかかりにしてそこから台本作っていくのに、それを読ませるための文面にした途端に、なにもなくなって、そちらを頼りにしなくちゃいけなくなります。あれが、本当にストレスですよね。
いながき:だから、いわゆるハリウッド・メソッドみたいなシド・フィールド的方法(※)って、そういうストレスを感じずに済む方法だと思うんです。要はその大量生産のラインに乗っかって書けばある程度面白いものはできますよというやり方ですよね。
これにはもちろんお世話になったりもします。開始何分でプロットポイントがあってというアレは、とてもシステム化されているものですよね。
ただ、そのシステムは今言ったぱっと思いついたメモ書きから拡がっていく映画的なものがどんどん殺されていく作業だというのはすごくよくわかりますね。
(※シド・フィールド:アメリカの脚本家、シナリオ講師。脚本術としてまとめられた「screenwriter’s workbook」が多くのシナリオ作家に受け入れられている)
守屋:あれ、なんとかなんないのかなぁ。
いながき:これは共同作業というもののテーゼだと思うんですよね。
脚本とそれ以外の人に対して見せるものってどうしても必要になってしまうのかもしれません。
守屋:だって、台本読めばいいじゃないですか。台本読んでくれよって思うんだけど。
いながき:(笑)そうですよね。じゃあ、なんでプロットが必要なんだろう。
守屋:時間がないからじゃないですか。だって、台本読んだら一時間はかかりますもんね。プロットだったら、ペラペラって読めますから。
いながき:じゃあ、時間の制約がないとしたら、プロットよりシナリオを書いた方がいいですか。
守屋:今ちらっと考えてしまいました。どうでしょうね。
いながき:僕はシナリオを書きたいタイプだから、シナリオを読んでくれればありがたいんだけど、最近はですね、みんなが理解できるハコをまず出すのが折衷案なのかなって感じたりしています。
守屋:みんなが理解できるハコか。どれくらい作りますハコって。
いながき:僕は頭からお尻まで作ります。特にかっちりした仕事の場合は。ただ、そのままシナリオにはなりませんけど。
守屋:俺もちゃんとハコ作んないとだめなのかな。
一番初めにピンク映画のシナリオコンクールで賞をもらったときとその次まではちゃんとハコ作ってたんですよ。特に一本目の台本はハコを作ったら書くのが楽で、あとは書くだけでよかったんですよね。あの感じは確かに最近ないですよね。
いながき:実は僕はハコ書きに一番時間がかかるんですが、考えてみれば当たり前の話なんですよね。ただハコってシナリオより文字数は圧倒的に少ないわけで、ハコなら二三日あれば書けるよねという発注も少なくありません。そんなわけがないんですけどね。
守屋:考えるプロセスってあるんですよね。なぜそれがこんなに共有されないんだろうな。
いながき:あと考え方もあるじゃないすか。考え方こそメソッドに還元できないから、人それぞれなんですよね。つまり、考えを絞り出す方法ですね。
守屋:俺は朝起きた瞬間が勝負みたいなところがあって、その時になにも思いつかないと一日無駄にするみたいな感覚があります。
朝起きた時に、それまで全然思いもしなかったセリフがぱっと思いついて、それがとっかかりになって次のシーンがコロコロコロって転がっていくことが寝起きに多いんです。それがない朝って絶望的ですよね。
いながき:寝起きですか……。僕は実は延々寝続けたりします。寝ながら考えてるんですが、怠けていると誤解されやすいんですが。
ともかく「まんが島」はいきなりシナリオだったんですか。
・『水澤とまんが家を目指していた』
守屋:ペラ一くらいのアイデア書きはあったんですけど、ちゃんとしたハコは作ってないですね。
2011年、震災があった時には、草稿がありましたね。で、本編に爆発があるから、これできないなって思ったのを覚えてます。そこから、いろいろ仕事をしながらですが、2013年に入るまで直してましたね。だから二三年とかですね。
いながき:じゃあ、もうその時から、自分で撮ることは決めていたんですよね。
守屋:そうですね、自分で撮って、自分で出ると決めていました。
水澤(水澤紳吾さん)が小学校の同級生で……、水澤と二人で出るというのは決めていました。
いながき:え?! そうなんですか。
守屋:水澤と一緒に小学校の頃まんが家を目指していたんですよ。野球選手になりたいとかそういうレベルですけど。一緒にまんがを描いていたというのが、大本の元のネタというかやり始めたきかっけなので、俺が出るというのは最低条件だと思ってましたね。
一瞬、俺が出ない方がいいかもしれないと制作の途中で感じたんですけど、今回は他の人が考えつかず、これはやるしかないと思いましたね。
いながき:その他の役者さんはどう決めて、どう声をかけていったんですか?
守屋:書きながら、セリフが松浦(松浦祐也)さんの声に聞こえてきたりして、そこで恐る恐る電話をし、台本を見せて、読んでもらって、というのがほとんど全員ですね。邦城さん(邦城龍明)だけは、全然当てがありませんでした。クリストファー・ドイルが撮影をやった「おんなの河童」というピンク映画に参加した時に、主役の正木佐和さんと知り合って、正木さんの事務所のホームページで邦城さんを見つけて、正木さんに電話して「邦城さんってどういう人?」って聞いて、インの二週間前くらいに声をかけました。
いながき:みなさん、普段から知ってる方たちなんですか。
守屋:どこかの現場で会って、そういう一回きりの記憶で、今でこそ、宣伝でみんなにひっきりなしに会うけど、松浦さんに電話したのも五年ぶりでしたね。
いながき:そうなんですね。
守屋:川瀬さんはピンク周りでいちばん会ってたかな。それでも半年に一回とか、くらいですかね。
・『おっぱいを揉みたくなるようななにか』
いながき:もともとピンクが多かったんですか。
守屋:一番最初にデビューさせてもらったのが、ピンク映画の脚本なんですよね。演者で呼んでもらうこともありますし、どうしてもピンク映画の世界抜きには自分はいないなという感じがします。
もちろん、沖ちゃん(沖田修一)とか冨永さん(冨永昌敬)の現場に呼んでもらったり、台本を一緒に作ったりはしましたが、やっぱりピンク映画の人たちに台本を選んでもらったっていうのがでかいんですよ。
いながき:僕はまったくピンク映画の世界に接したことがなくて、どういう感じなんですか?
守屋:台本はカラミがなきゃいけないですよね。カラミのシーンって話が進まないじゃないですか、セックスをしてるだけだから、そのセックスの間になにかしら話のきっかけになる事件を起こすんですけど、でも結構な分量の中にその一言ですよね。あとは体位だとかを一生懸命書かなきゃいけないんですよね。
いながき:やっぱり書かなきゃいけないんですね。
守屋:うーん、やっぱり書きますね。キスをするセックスとしないセックスではずいぶん違うじゃないですか。
歩いたり話したりしているシーンって、ストーリーを転がすためのシーンじゃないですか、でもセックスのシーンって違うんですよね。セックスをするためのシーンだから、すごく書きづらいというか、体力がいりますよね。なにか必然性がないと人物って動かないじゃないですか。そこで、例えば、おっぱいを揉みたくなるような何かがないとおっぱいが揉めないから、ということを考えながら書いてますね。
いながき:デビュー前に、一度ピンクのシナリオを書かないかと言われてトライしたことがあるんです。その時、勉強不足すぎて、挫折しちゃったんですよ。結局、カラミのシークエンスになると、途端に筆が止まるんです。とても体力がいりますよね。
守屋:そうなんですよ、
いながき:アクションシーンと似てるってことなのかな。
守屋:たしかにアクションですね。
いながき:日本映画でアクションシーンを書くことって、相対的にマレだと思っています。だから書き慣れていないんじゃないかと思うんです。
日本の作家さんってセリフがうまい人は無数にいるんだけど、例えばアクションやカラミをうまく書く人ってどれくらいいるのかなと思いますね。
つまり、おっぱいを揉むなら、おっぱいを揉むきっかけなり動機なりが必ずいると、作家の生理として思うじゃないですか。
殴るなら殴るなりのきっかけが必要ですよね。いきなり殴るならその人はキチガイであり、キチガイを描くならばそれでいいのですが、そこには必然性がありますよね。
守屋:動機みたいなものがない時もあるじゃないですか。そういう時は「おっぱいに目が止まる」みたいなト書きを三行くらい作って、それでやっと揉むわけです。本当はその三行っていらないんだけど、でもその三行がないと、四行目が出てこない。カラミのシーンはそういうことばっかりですね。
でもまあ、書きたくないわけじゃないし、やっぱり、ピンクはカラミが見せ場だから、そこにむかって話も組んでいるし、苦労しますね。
(第二回はこちら)
(第三回はこちら)