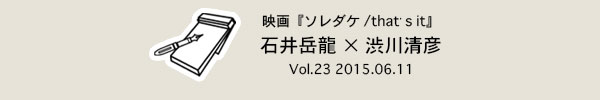最終回
石井岳龍監督作品、映画『ソレダケ/that’s it』が公開中です!
主演は、染谷将太さん。
脇を固めるのは、村上淳さん、渋川清彦さん、
水野絵梨奈さん、そして綾野剛さん。
さて、どんな物語が繰り広げられているのでしょうか。
ぜひ、劇場で目撃してください!
実は、微力ながらわたくし、いながきも脚本で
参加させていただいております。
普段は自分の作品、ここまで言いませんが、
めちゃくちゃ面白いのです。
必見です。
そこで、公開を記念して、『コギトの本棚』では、
四週に渡って、石井岳龍監督、渋川清彦さんを
お迎えした対談という形で、
インタビューを掲載いたします。
今回は、最終回。
読んでから観るか、観てから読むか、
他では読めないかなり突っ込んだ深いお話、
ぜひ、お楽しみください!
(文/構成 いながききよたか)

映画『ソレダケ/that’s it』
『狂い咲きサンダーロード』(80年)、『爆裂都市 BURST CITY』
(82年)などで世界を震撼させた"邦画界の革命児"石井岳龍監督
(=石井聰亙)が、遂にロック映画の舞台に帰って来た。
『生きてるものはいないのか』(12年)『シャニダールの花』
(13年)などの不条理なオルタナ世界の探求から一転、無類の
音像を構築し続けケタ外れの独創性を発揮するバンド
bloodthirsty butchers(ブラッドサースティ・ブッチャーズ)の
リーダー、故・吉村秀樹からの熱烈なラブコールのもと完成させた
叛逆の青春物語、それが本作『ソレダケ / that's it』である。

石井岳龍 (いしい がくりゅう/1957年1月15日生まれ )
神戸芸術工科大学教授。改名前の石井聰亙(いしい そうご)の
名で広く知られている。福岡県福岡市生まれ。福岡県立福岡高
等学校、日本大学藝術学部中退。1976年、大学入学直後、
8mm映画デビュー作 『高校大パニック』が熱狂的な支持を得る。
デビュー以来の鋭い表現手腕は、映画に留まらず、ミュージック
クリップ、ビデオアート、写真、ライブ活動等、 様々なメディア
で発揮され続けている。尖端的な音楽と、風景や光の情景を
ミックスさせた映像表現手法は、「実験的」と評されながらも、
特に同じ業界の人間 や、アーティストからの評価が高いことでも
有名。ちなみにクエンティン・タランティーノも石井聰亙を敬愛
している。 代表作に、『狂い咲きサンダーロード』(1980年)
『爆裂都市 BURST CITY』(1982年) 『逆噴射家族 』(1984年)
『ELECTRIC DRAGON 80000V』(2001年)
『生きてるものはいないのか』(2012年)
『シャニダールの花』(2013年)など。

渋川清彦 (しぶかわ きよひこ、1974年7月2日)
群馬県渋川市生まれ。
「KEE」の名前でモデルとして「MEN'S NONNO」や「smart」
などの雑誌で活躍。1998年『ポルノスター』(豊田利晃監督)
にて俳優デビュー。2006年より、現在の芸名に改名。名前 の
由来は自身の出身地である、群馬県渋川市から。(ちなみに、
2011年より同市の観光大使も務めている。)
主な出演作は、『ナインソウルズ』(2003年)、
『せかいのおわりworld' end girl friend』(2004年)、
『実録・連合赤軍あさま山荘への道程』(2008年)、
『PASSION』(2008年)、『フィッシュストーリー』
(2009年)、『蘇りの血』(2009年)、
『ゴールデンスランバー』(2010年)、
『惑星のかけら』(2011年)、
『生きてるものはいないのか』 (2012年)、
『11.25自決の日 三島由紀夫と若者たち』(2012年)、
『俺俺』(2013年)
☆誰が見るか。
石井:自分じゃわからないな。この映画は誰が見るんだろうね。
渋川:そういう意味で言えば、石井さんのファンは絶対見ると思うし、それ以外の部分、たとえば、人気のある綾野君のファンにも見てほしい。そこで、たとえばオレが人を呼べるならば、それでもいいと思う。ギャルみたいな人達が反応しても面白いと思う。
石井:たくさんの人に見てほしいな。

渋川:人気者がいて、その人に反応して見に来てくれるというのは、いいと思う。
いながき:出会いがしらというか、化学反応というか、そういうものがあるところが映画の良さでもありますよね。
石井:この映画の中の面白さというのを、的確に、前もって、宣伝できないということはあると思うのね。物語の構造上、ネタばれがコワいから、言えないという部分がある。なかなか全体のプレゼンテーションが難しいと思う。
欲張ってる映画なんだけど、それがいい方に、行って欲しいんだけどな。
渋川:そればっかりは、どんな力が働くかわからないよね。
石井:今は、情報をちゃんと出せばいいかっていう問題があると思う。出さない方がいい場合もあったりする。ちゃんと出さなきゃいけない場合もある。宣伝の規模も大作と比べたらほぼゼロというほど違う。だったら、情報を出さない方がいいかもしれない。これだけ振り切ってるんだから、ポスタービジュアルもこんなんだし、今時ないでしょ、こんなの。
いながき:ないですね。
石井:70年代だよ、これは。
渋川:完全にそうですね。見た事のある懐かしい感じ。

石井:これで、勝負しようって、本当に大丈夫か!って思う。一歩間違ったら、ねえ……。でも、おかげさまで、初日は、席がなくなってきてるみたいだよ。(インタビュー時5月1日)
いながき:ほんとですか! 個人的にチケットとろうかな。
☆シナリオ作り
いながき:シナリオ作りについてなんですが、シナリオに関する石井監督の作法を、ずっと聞いてみたいと思っていました。今まで、たくさんのライターの方と共作なさってきたと思います。作り方には、メソッドがいろいろありますが、石井監督が大事にしていることはありますか。

石井:ライターも一人ずつ違うんで、俳優さんもそうだし、スタッフでも同じですが、一緒にやって力を最大限に発揮できる方法が一番正しいと思ってますね。だから、ある程度、こうじゃないかと思ってる部分はありますけど、具体的にやってみて、それを修正していくというか。
いながき:実は、かなり以前に、まだ駆け出しのころ、石井監督ととある企画を開発したことがあります。プロットを書かせていただいたんですが、力不足すぎて、歯牙にもかけられなかった思い出があります。でも、僕の中では、大事な出来事でした。
石井監督の御自宅に何度かうかがって、その時に、監督の背後にある本棚から、笠原和夫さんの『昭和の劇』という本を手にとり、「今、こういうふうに書ける脚本家はいないかな」と、仰っていました。(笠原和夫:昭和を代表するシナリオライター、代表作に『仁義なき戦い』、『県警対組織暴力』など)
石井:(笑)
いながき:笠原さんの書き方というのはやはり理想でしょうか。
石井:徹底的な設計図として、完成度高く組み上げてもらえるんだったら、なにも言うことはないです。
いながき:(恐縮)
渋川:でも、『ソレダケ』のシナリオは、キャラクターのエネルギーが完全に闘ってるもんね。『仁義なき』もそうじゃん?

石井:一つ、今回、開眼したことは、登場人物に対する愛情だと思うよ。
あるいは、描く世界に対する愛情。それが、徹底的に隙なくないと、生まれてこないと思う。たとえば、「このセリフでいいんだろうか」ってさ、あるいは、「もっと、このキャラクター生かしたい。これでいいんだろうか、もっと面白くなるんじゃないだろうか」っていう時には、そのキャラクターを徹底的に愛してないと面白さは生まれ来ない。何が正しい方向かというのは、キャラクターに対する愛情が足りないと、出てこない。勝手に、このキャラクターはこの程度と高をくくるんじゃなくて、さっきも言ったけど、どんなに悪人でも、どんなに非人間的でも、自分が描きたい人物として描く以上は、とにかく相手の懐深くまで飛び込んでいって、距離感を無くしてケツの毛まで知らないとさ。そこまで見ればおのずとこぼれてくると思う。
いながき:今回、ものすごく勉強させてもらったんです。というのは、劇中で綾野剛さん演じる千手完が、ブルース・リーについて言及するのですが、シナリオ作りで少し間が空いた時、石井監督から、メールで「ブルース・リーに関する哲学的探査を続けておいてください」と通達がありました。
渋川:(笑)

いながき:図書館に走り、ブルース・リー関連本を借りまくって、読み続けました。やはりそこまで深めなければダメだということを勉強したんです。
恵比寿にしても、セリフの中でとある登場人物が出てきますが、それは知人たちにいろいろエピソードを取材して、生のモデルがいるんです。そういうバックグラウンドの追及みたいなことが大切なんだと思いました。
石井:当然だと思う。シナリオの面白さはそれをどこまでやったかということだと思うよ。自分が本当に芯まで知ってる世界だったらね、アイデアがおのずから湧いてくると思うけどね。
いながき:そればっかり書いてられませんもんね、限界があります。
石井:ドラマをやる人間の宿命として、突っ込まなきゃいけない。キャラクターが面白いか否かは、その人間に対する本当の愛情があるか否かだけだと思うよ。本当の愛情は、時に適正な距離感や突き放しも必要だし。
その上で、俳優さんに倍増してもらうんだと思う。出来る俳優さんたちには、よりかかっちゃう部分があるけど、本当はいけない。シナリオの段階で、演出の段階で、百パーセント以上、行ってないと。
いながき:『ソレダケ』に関しては、僕のシナリオ人生では、エポックメイキングな作品だったのですが、では、俳優さんたちに関してはいかがですか?
☆「もっと……、その先に」

石井:今回は、染谷くん、渋川くん、村上くんありきの企画だったので、この三人は作品の原点ですね。
その上で、それに対抗する女優さんは誰かとか、それに対抗する敵は誰かということでした。
しかし、これだけの俳優陣を前に、南無阿弥役の水野絵梨奈さんは、頑張りましね。この四人相手に、新人女優とは思えない演技でした。
逆にシナリオ作りが難しかったんだろうな。
経緯としてね、安易だったけど、ライブプラスドラマの進行というのは、ぱっと書けたんだよ。それで勝負するしかないと思ったし、ベースとしてブッチャーズのアルバムがあったので。
渋川:オレは、そこから始まってたと思ってたから、ブッチャーズを聴きこんだというのもあったし、物語もそうだけど、ブッチャーズから始まってるんだと思ったから、音楽を理解しようというところから始めたんだよね。
石井:最初の企画では完全にそうだった。80分くらいのものだったかな。その時に、ブッチャーズがライブでは、「ソレダケ」という曲をよくやっていた。あと、「6月」という曲、個人的には「curve」や「ocean」が好きだったし、それを総合して、考えてたんだけど、吉村君の死でプツンとそれがなくなった時に、「じゃあ、なにするんだよ」と考えて、一番興味があって、ブッチャーズと関連していることは、「アンニュイ」とかから発想したホームレスの男女だった。吉村くんと田渕さんは、どんなに逆境でも淡々と熱くマイペースでやるんだろうなというイメージがあったから。そういう精神性を感じて、ホームレスの男女ということが出てきたんだと思う。
たとえば「10月」とかは、完全に深作さんの『仁義なき戦い』とかを想起させるような、いきなり全開という曲でしたよね。
渋川:すごいですよね、あれは。歌詞も見事に染谷に合っているという。
石井:ほら、あろうことか『君は叫ぶ』で、渋川君は叫んでるし、ああいうのはピタっときてる。もうこれしかないみたいなね。

いながき:『ソレダケ』は、テーマから言うと、社会派っぽいことになりがちかもしれませんが、できあがった作品を観ると……、
石井:なってないよね。
いながき:なってないし、どちらかというと、青春映画に近い感覚があります。
石井:オレも、『トゥルーロマンス』とか、近いなと思った。
いながき:それは、かなりブッチャーズないし吉村さんの楽曲にひっぱられた部分なのかなと思います。やっぱり、聴きながら書いていましたし。

石井:社会的なメッセージ性はある、ベースにパンクがあるから。だけど、曲としては、自分の本当に素直な心情、記憶の心情みたいなことが、純粋に表われてるので、そのあたりが『青春』というか、どうしてもほとばしる気持ちというものに繋がってるのかもしれない。でも、たとえば、女の子と一緒になっても、子供ができても、ロックとして生きるんだという、静かな彼の決意が、オレはすごくいいなと思うんだよね。人を攻撃しない、だけど、激しい、「これでいいんだろうか?」と自分に問うてみることが、すごく素敵で、チャーミングだと思うんだよね。そこは、この映画のポイントだと思う。
アクション映画として、対立構造は産まないといけないので、どうしても敵役というのは、作らなきゃならなかったんだけど、敵役のあり方も、なかなか難しいなと思いましたよね。
いながき:一番、悩んだのが、猪神であり、千手の在り方でした。

石井:そうだね。猪神については、あるいは千手については、いろいろあったね。敵役は難しいな。課題だな。

いながき:敵役のことに関して、ぶっちゃけて言うとですね、書いていて、「これでいいだろう」と思う瞬間があるんですけど、石井監督は全然許してくれません。「考えが及んでいませんね」、「停滞してますね」と、ストレートに鼓舞してくれました。上品な言葉でのダメ出しが出てくるので、余計、くらうんです。
石井:いや、悪は深いんだよ。悪の深さが、人生の深さなんだよね。
いながき:千手のセリフも、「これは、よく聞いたことのあるセリフだから変えてください」と。
石井:そうだよね、当たり前じゃつまんないよね。
いながき:敵役は難しいな。
石井:悪が人生の陰影をつけるんだよね。
渋川:逆に、自分が納得したのに、そこに何かを言ってくれるという人がいるって、すごくいいことだと思う。
いながき:本当にそうですね。

石井:いや、もっともっともっとって、思いますね……。
いながき:では、もっと、話し足りないということで、この続きは、ご飯でも食べながらにしませんか?
それでは、今日はありがとうございました!
『ソレダケ/that’s it』の成功を祈って!
(この後、キングレコードの長谷川さん、ライブ・ビューイング・ジャパンの川口さんも飛び入り、お話は、吉村さんの思い出、そして、各々の音楽観や、映画観に話が及び……。ここにはすべて書き起こせませんが……。
とにかく、『ソレダケ/that’s it』、よろしくお願いいたします!
石井監督、渋川清彦さん、ありがとうございました!)