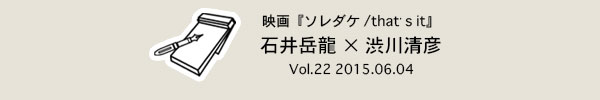第三回
石井岳龍監督作品、映画『ソレダケ/that’s it』が公開中です!
主演は、染谷将太さん。
脇を固めるのは、村上淳さん、渋川清彦さん、
水野絵梨奈さん、そして綾野剛さん。
さて、どんな物語が繰り広げられているのでしょうか。
ぜひ、劇場で目撃してください!
実は、微力ながらわたくし、いながきも脚本で
参加させていただいております。
普段は自分の作品、ここまで言いませんが、
めちゃくちゃ面白いのです。
必見です。
そこで、公開を記念して、『コギトの本棚』では、
四週に渡って、石井岳龍監督、渋川清彦さんを
お迎えした対談という形で、
インタビューを掲載いたします。
今回は、その三回目。
読んでから観るか、観てから読むか、
他では読めないかなり突っ込んだ深いお話、
ぜひ、お楽しみください!
(文/構成 いながききよたか)

映画『ソレダケ/that’s it』
『狂い咲きサンダーロード』(80年)、『爆裂都市 BURST CITY』
(82年)などで世界を震撼させた"邦画界の革命児"石井岳龍監督
(=石井聰亙)が、遂にロック映画の舞台に帰って来た。
『生きてるものはいないのか』(12年)『シャニダールの花』
(13年)などの不条理なオルタナ世界の探求から一転、無類の
音像を構築し続けケタ外れの独創性を発揮するバンド
bloodthirsty butchers(ブラッドサースティ・ブッチャーズ)の
リーダー、故・吉村秀樹からの熱烈なラブコールのもと完成させた
叛逆の青春物語、それが本作『ソレダケ / that's it』である。

石井岳龍 (いしい がくりゅう/1957年1月15日生まれ )
神戸芸術工科大学教授。改名前の石井聰亙(いしい そうご)の
名で広く知られている。福岡県福岡市生まれ。福岡県立福岡高
等学校、日本大学藝術学部中退。1976年、大学入学直後、
8mm映画デビュー作 『高校大パニック』が熱狂的な支持を得る。
デビュー以来の鋭い表現手腕は、映画に留まらず、ミュージック
クリップ、ビデオアート、写真、ライブ活動等、 様々なメディア
で発揮され続けている。尖端的な音楽と、風景や光の情景を
ミックスさせた映像表現手法は、「実験的」と評されながらも、
特に同じ業界の人間 や、アーティストからの評価が高いことでも
有名。ちなみにクエンティン・タランティーノも石井聰亙を敬愛
している。 代表作に、『狂い咲きサンダーロード』(1980年)
『爆裂都市 BURST CITY』(1982年) 『逆噴射家族 』(1984年)
『ELECTRIC DRAGON 80000V』(2001年)
『生きてるものはいないのか』(2012年)
『シャニダールの花』(2013年)など。

渋川清彦 (しぶかわ きよひこ、1974年7月2日)
群馬県渋川市生まれ。
「KEE」の名前でモデルとして「MEN'S NONNO」や「smart」
などの雑誌で活躍。1998年『ポルノスター』(豊田利晃監督)
にて俳優デビュー。2006年より、現在の芸名に改名。名前 の
由来は自身の出身地である、群馬県渋川市から。(ちなみに、
2011年より同市の観光大使も務めている。)
主な出演作は、『ナインソウルズ』(2003年)、
『せかいのおわりworld' end girl friend』(2004年)、
『実録・連合赤軍あさま山荘への道程』(2008年)、
『PASSION』(2008年)、『フィッシュストーリー』
(2009年)、『蘇りの血』(2009年)、
『ゴールデンスランバー』(2010年)、
『惑星のかけら』(2011年)、
『生きてるものはいないのか』 (2012年)、
『11.25自決の日 三島由紀夫と若者たち』(2012年)、
『俺俺』(2013年)
☆ラテン・アメリカ
いながき:そういえば、石井監督は、ラテンアメリカ文学的世界観などは?
石井:そう、好きなんだよね。メタフィクションやサイバーパンク的世界観も。現実や人間を、魅力的な嘘としてどう表現するかの世界観。
渋川:ラテンアメリカ文学的世界観というのは、ざっくり言うとどんな感じですか?
いながき:マジックリアリズムと言われる世界観ですね。作家で言えば、マルケスやボルヘスですね。
石井:濃いのよ。
渋川:濃い?

石井:普通の僕らのリアルだと、そんなこと起こらないよね、こんなことないよねっていう出来事が平気で起こるんだよね。起こる事件が、ちょっと派手なの。
渋川:物語がですか。
石井:キャラクターもですね。たとえばね、恵比寿みたいな人って、僕は実際いると思うんだよね。横浜とかで、見た事あるし、博多にもああいうヤツいるんだよ。だけど、普通の人は、そういう人が横にいると思わないじゃない。本当は実際にそういうキワの人間は確かにいるのにだよ。
ラテンアメリカの文学や映画は、人間のあり様を沸騰させているっていうか、キャラクターが解き放たれているんだよね。それがオレは好きなんだよね。日本人って、割と地味とか、控え目なリアルとかが好きじゃないじゃないですか。でも、ラテンアメリカ文学って、キャラクターが全面解放されちゃうので、それを、ドラマにしちゃうと、ちょっと濃いんだけど、オレは好き。ウソのつき方が派手なんだよ。
いながき:それでいて、ファンタジーではなく、リアルに根ざしているものなんですね。
石井:博多の下町、俺が生まれ育った周りとか完全にそういう雰囲気があった。
渋川:博多はそれっぽいですね。
石井:近畿にもそういう部分がある。横浜でも、トンデモない人、いるんだよね。頭に魚みたいなものを一杯付けてる人とかね。そんなおっさんがさ、歩いてるんだよ。あり得ないんだけど、横浜だったら、いるなぁみたいな。実際、オレ見たし。そういう人を映画に出すと、ウソくさいというか、そんなのウソだと言われる。でも、本当はいる。
ラテンアメリカの文学とかって、ありえないようなことが平気で起こるんだけど、でも、よく考えると、人間ってそういうことするかもしれないなって思えるものばかりなんだよね。生者と死者とが普通に会話したり、現実が妄想と合体してもっと面白かったり、怖かったりに拡大する世界。これってまんま現実のデフォルメである映画世界に似ていると思う。

いながき:そうですね、本当に。
石井:今の日本で、一番近いというと、『私の男』の桜庭一樹ですかね。あと、やっぱり安部公房とかはそうですね。ありえなさそうだが、一番人間の本能に近い欲望まで取り入れたリアルさの追究。
渋川:中上とかはちがいますか?
石井:中上健次も、そういう面が強いよね。
渋川:中上健次の作品に出てくるキャラクター、めちゃくちゃ魅力的じゃないですか。
いながき:当時、大江健三郎が、元々フォークナーなんかが理想だったわけですけど、マルケスの『百年の孤独』を読んで、めちゃくちゃ衝撃を受けたという話を聞いています。名前も、犀吉とつけたり、鳥(バード)とつけてみたりというのも、その影響下なのかもしれません。それこそ、安部公房などは、ラテンアメリカの薫陶を受けているんじゃないでしょうか。中上も完全にその系譜にあると思います。
渋川:百年から、千年にいったわけだ。

いながき:あ! まさにそうですね、『千年の愉楽』ですもんね。
石井:中上健次は、たとえば、熊野という、隔絶された面白く濃い土地がバックボーンにあるじゃない。
渋川:今、オレ、熊野おっかけてるんですよ。火まつりは毎年行ってますね。すごく面白くて、熊野、新宮の土着的な雰囲気がめちゃくちゃ面白くて、あそこの祭りも、若い奴らが、たいまつで殴り合って喧嘩してるからね。
石井:そんなのありえねえよって言われるんだけど、そういうどこか人間の中で、はみだしてる過剰な部分というのは、絶対もってるでしょう? 持ってるのに、たとえば、東京などで日常生活を送っていたりとか、普通にみんなと日常をうまく暮らしていこうという中では、過剰な部分はダメと言われ、抑えられるわけです。それが、たとえば祭のときに、わっと発散されるんだよね。ラテンアメリカの芸術って、キャラや日々がお祭り的なんだよね。それが普通として組み立てられている。
『ソレダケ』という映画も、ある種そういう状態というのを、設定すれば、いわゆるロックの勢いのある空間と、ドラマというものが作れるんじゃないかっていうね。馬鹿馬鹿しい大ウソでもね。

いながき:祭という祝祭の場とロックって似ていますものね。
石井:その通りだよ。ロックって、元々でかい音出すとか、叫ぶとか、人間にはね、そういうことが、絶対に必要なんだけど、日常生活の中で、でかい音を出し、叫ぶということをすると、危ない人、犯罪者と思われてしまう。だから、出来ないわけでしょ。みんな仲良くおとなしくやっていきましょうよ、ということになる。まあ、そうだよね。たとえば、横でわあわあ大声出されたりしたら、うるさいわけじゃん。だけど、そういう人達がいなければ、そういう表現が無ければ、俺たちは、多分、どこかで間違いを犯してしまうことになるわけだから、絶対そういう場が必要なんだけど、現代では、許されない。みんな、小さい世界に閉じこもるしかなくなる。そうすると、溜ると思うんだよね。
渋川:話は変わるかもしれないんですけど、オレ、映画で西成にずっといってたんですよ。あそこは街の度量が大きいんですよね。そういう人、普通にいるけど、全然苦にならないんですよ。
石井:そこだけ、ラテンアメリカになってる?

☆映画と思想、暴力
渋川:すごく楽しいんですよね。いまだに、シャブ売ってるやつとか、道端にいるし、仕事にあふれたやつとか、朝から飲んでるし。でも、今、西成も、クリーン作戦ってのがあるんですよ。それに抵抗する左翼のやつらが映画撮ろうっつってんですよ。それこそ、川瀬陽太さんが主演で、オレ、呼ばれて行ったんですよ。ほんと、面白くて、そいつらバカで。京都の奴なんだけど、ほら、京都って左の思想が強くて、「僕、左翼っすから」みたいなこと言いながらさ、すごい純粋でさ。
いながき:そういう左翼の人達が、クリーン作戦に反対するって、面白いですね。
それに関連するかどうか、わかりませんが、僕は、実は、疑問があります。石井監督や渋川さんは、ともするとギャングスタというか、オラオラしてるっていうか、そういう風に、誤解されがちじゃないですか。でも、こうして仕事でご一緒させてもらうと、ものすごく上品、いや、上品という言葉でも表せないんだけど、なんていうのかな。

渋川:それ、すごくわかる。石井さんの作品でもそうなんだけど、なんか、裏はすごくあるんだけど、直接的には言ってない。それって、直接的に言うよりも、メッセージがあるじゃないですか。それって、一番、かっこいいというか、好きですね。

石井:映画を作ってるんですよ。映画の現場に携わってるから、思想家じゃない。アジテーターでもない。自分のやってることに忠実にありたい。その中で、自分の好きな世界とか、好きな人間達、そして間違った方向に進んでるかもしれない世界と、うまくやっていけないかなということは考えてる。
渋川:多分、品っていうことってそうだと思う。
たとえば、映画で、「原発反対」ってモロ表に出すと、オレ、それは充分わかるけど、なぜか、「いいや」ってなったりするもん。
いながき:すごくわかります。「わかるけど、いいや」って、この感覚、すごくあります。
渋川:またそれも、難しくて、昔の黒木和雄の『原子力戦争』を見ても、あれはあれで好きだしね。なんなんだろうな。
いながき:今回の映画を書いている時に、一つ感じた事があります。今回、暴力シーンが多いじゃないですか。でも、監督は、暴力シーンというのは、そんなに好きじゃないとおっしゃるわけです。
石井:そう、好きじゃない。
いながき:どこかに境界線があって、それを越えるのは、絶対だめだとおっしゃるんですね。ということを守ったシナリオになったんですよね。
石井:映画として、暴力を描きたいわけじゃなくて、ドラマとして、人間は時に暴力的になるものだし、それが表現として活きるのであればいいと思う。映画をやっているんだから、きれいごと言うなよとも思うんだけど、本当に人を傷つけたいわけじゃないからね。今回の表現などは、本当にキワだと思うんだけど、やるからには、主人公達を苦しめる、あるいは、綾野君がやった千手の非情さですね、彼がいかにメカニカルになっているかということをみせなきゃいけないですよね。まあ、おとなしい表現になってるとは思うけど、かなり、個人的には苦しかったよね。
編集で、何回も何回も、見なきゃいけないからね。

渋川:しんどいですよね、それは。
石井:拷問を受けているみたいで、夢見が悪かったよ。だけども、普通にキレてる状態といえば、あんなもんじゃないだろうね。その辺は難しいところだね。
いずれにしろ、今回は、避けて通れなかった。スタッフの中にも、音響の猪俣さんがまったくダメで、「ここは、音がつけられない!」って。僕は「ここ、もっとつけてください」って言うんだけども、「オレは無理だ」って、助手の人につけさせたみたいよ。
難しい問題だよね。ただ、表現としてはね、人間を普通の評価というか、普通の見方をするのは、だめだと思うんだよね。『羊たちの沈黙』のアンソニー・ホプキンスが、人間を食べてしまうという博士を演じる時に、こいつは嫌いだとか、こいつは悪いやつだとか、こんな人間は信じられないと、自分の勝手なレッテルを押したら、演じられないと思うんだよね。やるからにはその人を徹底的に愛さないといけないと思うんだよね。悪いとか善いとかは、人間の勝手な想像だから、そこをとっぱらって、なぜ、この人は人肉を食べるのかということを徹底的に考えないと演じられないし、面白くないと思うんだよね。そこにブレーキをかけても、なんのリアリティも生まれない。
心のキャパの問題かもしれない。そのキャパがなければ、やらなければいいし、無理してやったんじゃ、きちんとはできない。

いながき:石井監督は、決定的に、ハネケとかラース・フォン・トリアーという系譜ではないと思うんですよね。
石井:今は好きではないね。でも、表現としては、すごいなと思う部分は大いにある。ただヨーロッパ人のああいうところってちょっとついていけない部分がある。それが評価されるのもわかるし、彼らはあれを無理してやってないから、評価されるんだと思うしね。彼らにとって、とっても、重要なことで、そういう世界に生きてるっていうことだからね。
渋川:オレは、衝撃でしたね。ハネケの『ファニーゲーム』は。
好きか嫌いかわからないですけど。そっから追っかけたんですけど、なかなか先に進めなかったっすね。
石井:「いきなりの暴力」って、現代社会は、その通りなのかもしれないけど、それを映画で見なきゃいけないのかどうかというのは、わからない。すぐれた映画だということはわかる。けれど、それをオレが観たいかどうか、あんまりかな。
いながき:ただ、彼らって、掛け値なしっていうか、狙ってやってないというか、あれしかできないからやってる感じがあるんですよね。
石井:信じてるんだよね。『ピアニスト』観てても、「うわー、すげえ」と思うよ。俳優たちも含めて。でも、自分が撮りたいかというと、撮りたくはない。
渋川:それこそ、『生きてるものはいないのか』のとき、石井さんに教えてもらった『スリ』、ブレッソンでしたっけ。けっこう、おっかけてんですよ、オレ。
石井:ブレッソンは、好きだね。
渋川:『白夜』とか、こないだやってた『やさしい女』とか。二人が会話してる家の中で、外からひっきりなしに関係ない車の音が聞こえてくるんです。なんなんだろう、あの人の音って。

石井:ストイックなんだよね。自分のスタイルと、描きたいものが厳格にこれだ!というものが決まっていて、一切ブレずに徹底的に細部を描くというね。
いながき:『抵抗』もそうですね。
渋川:『ラルジャン』もね。
石井:ブレッソンは、すごく面白い。あれは全然OK。ハネケやラース・フォン・トリアーまで行くとね。トリアーは、初期のころ、すごく好きだった。パンクで重層的な映画でね。でも、ある時、一線を越えて、開き直ってるように見えてきた。
いながき:キーワードは『露悪』ということになると思うんです。つまり、狙いでやっちゃうと、センセーションを煽るということだけなので、映画としてどうなのかということを思ってしまいますね。
ともすると、今回の『ソレダケ』は、そういう風に見られる可能性もあります。しかし、そうではないと、自分では思います。切実な何かがそこにはあると感じています。

(いよいよ次週は最終回、シナリオとはどんなものか、そしてこの『ソレダケ』を誰にとどけたいのか。石井監督と渋川さんとのお話が極まります。お楽しみに!)