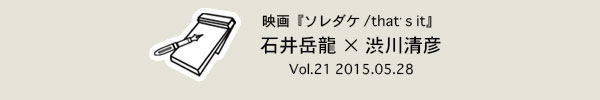第二回
5月27日より、石井岳龍監督作品、
映画『ソレダケ/that’s it』が公開中です!
主演は、染谷将太さん。
脇を固めるのは、村上淳さん、渋川清彦さん、
水野絵梨奈さん、そして綾野剛さん。
さて、どんな物語が繰り広げられているのでしょうか。
ぜひ、劇場で目撃してください!
実は、微力ながらわたくし、いながきも脚本で
参加させていただいております。
普段は自分の作品、ここまで言いませんが、
めちゃくちゃ面白いのです。
必見です。
そこで、公開を記念して、『コギトの本棚』では、
四週に渡って、石井岳龍監督、渋川清彦さんを
お迎えした対談という形で、
インタビューを掲載いたします。
今回は、その二回目。
読んでから観るか、観てから読むか、
他では読めないかなり突っ込んだ深いお話、
ぜひ、お楽しみください!
(文/構成 いながききよたか)

映画『ソレダケ/that’s it』
『狂い咲きサンダーロード』(80年)、『爆裂都市 BURST CITY』
(82年)などで世界を震撼させた"邦画界の革命児"石井岳龍監督
(=石井聰亙)が、遂にロック映画の舞台に帰って来た。
『生きてるものはいないのか』(12年)『シャニダールの花』
(13年)などの不条理なオルタナ世界の探求から一転、無類の
音像を構築し続けケタ外れの独創性を発揮するバンド
bloodthirsty butchers(ブラッドサースティ・ブッチャーズ)の
リーダー、故・吉村秀樹からの熱烈なラブコールのもと完成させた
叛逆の青春物語、それが本作『ソレダケ / that's it』である。

石井岳龍 (いしい がくりゅう/1957年1月15日生まれ )
神戸芸術工科大学教授。改名前の石井聰亙(いしい そうご)の
名で広く知られている。福岡県福岡市生まれ。福岡県立福岡高
等学校、日本大学藝術学部中退。1976年、大学入学直後、
8mm映画デビュー作 『高校大パニック』が熱狂的な支持を得る。
デビュー以来の鋭い表現手腕は、映画に留まらず、ミュージック
クリップ、ビデオアート、写真、ライブ活動等、 様々なメディア
で発揮され続けている。尖端的な音楽と、風景や光の情景を
ミックスさせた映像表現手法は、「実験的」と評されながらも、
特に同じ業界の人間 や、アーティストからの評価が高いことでも
有名。ちなみにクエンティン・タランティーノも石井聰亙を敬愛
している。 代表作に、『狂い咲きサンダーロード』(1980年)
『爆裂都市 BURST CITY』(1982年) 『逆噴射家族 』(1984年)
『ELECTRIC DRAGON 80000V』(2001年)
『生きてるものはいないのか』(2012年)
『シャニダールの花』(2013年)など。

渋川清彦 (しぶかわ きよひこ、1974年7月2日)
群馬県渋川市生まれ。
「KEE」の名前でモデルとして「MEN'S NONNO」や「smart」
などの雑誌で活躍。1998年『ポルノスター』(豊田利晃監督)
にて俳優デビュー。2006年より、現在の芸名に改名。名前 の
由来は自身の出身地である、群馬県渋川市から。(ちなみに、
2011年より同市の観光大使も務めている。)
主な出演作は、『ナインソウルズ』(2003年)、
『せかいのおわりworld' end girl friend』(2004年)、
『実録・連合赤軍あさま山荘への道程』(2008年)、
『PASSION』(2008年)、『フィッシュストーリー』
(2009年)、『蘇りの血』(2009年)、
『ゴールデンスランバー』(2010年)、
『惑星のかけら』(2011年)、
『生きてるものはいないのか』 (2012年)、
『11.25自決の日 三島由紀夫と若者たち』(2012年)、
『俺俺』(2013年)
☆『bloodthirthty butchers』
いながき:『ソレダケ/that’s it』に関してはブラッドサースティ・
ブッチャーズということは避けて通れない作品ですよね。
映画の誕生するきっかけに関しては、各媒体でお話されていると
思いますが、『ソレダケ/that’s it』が作られる前、石井監督の、
ブッチャーズに対する印象と関わりというのは、
どうだったんですか?
石井:オレは、オレたちに明日はないという感じで突っ走ってたんです。それが80年代の後半から行き詰っちゃったんだよね。30歳を迎えられないんじゃないかと思ったくらいです。
自分が30歳を越えるという意識がまったくなかった。ロックも全然聴かなくなったんだよね。
ブランキー・ジェット・シティやミシェル・ガン・エレファントくらいは、漏れ聞こえてきたけど、まさにブッチャーズとかナンバーガールといったバンドは、なんとなくしか知らなかった。だから、彼らとは接点がなかったんだけど、2006年になって、オレのDVDボックスを出だした時に、ルースターズ関連のこともあったから、いろんなバンドが出てくれたんだよね。特にブッチャーズとギターウルフ、DIP。DIPは、豊田利晃監督の音楽をやっていたから、気になってた。それから、フリクション。フリクションは好きでずっと聴いてたかな。あと、怒髪天、EXルースターズのロックンロール・ジプシーズ。
そういったバンドが出てくれたんだよね。
「ああ、こういう人達がオレの世界を好きでいてくれるんだ」っていうことがわかった。
そこから、また聴きだしたっていう感じかな。
彼らも、その時点で20年選手とかで、相当気合入れてやってて、生き残って、ぶれない人達だから、そういう意味では当然好きなわけだし、いいなと思いました。
ただ、一緒になにかやれるとは思ってなかった。だけど、『生きてるものはいないのか』で田渕さんの音楽を使わせてもらったり、吉村君と雑誌で対談したりということがあって、そういう流れで、依頼が来たって感じなのかな。

渋川:『生きてるものはいないのか』の時って、石井さんが、田渕さんに頼んだんですか?
石井:そう。彼女がやってるtoddleっていうバンドの既成の曲を使いたかったんです。
『kocorono』という映画が公開される時、吉村君と対談してさ、田渕さんのtoddleの曲をもらったのよ。ブッチャーズの「curve」という彼女のボーカル曲がものすごい好きだったんだけど、『生きてるものはいないのか』では、彼女のリードバンドtoddleの「chase it」っていう曲の方がいいんじゃないかと思いました。映画の冒頭、女の子の背中で始まるんで、女の子の曲の方がいいのかなと思ったり、あと、ギター音を流したかったんだけど、女性のギターの方がいいのかなと思ったんだよね。直感です。包み込むような世界っていうのかな、田渕さんのギターって、ソリッドなんだけど、母性を感じるんだよね。
渋川:「レクイエム」を聴いてて、惚れましたもんね。
それに、「ハレルヤ」を聴いた時に、コーラスが入ってくるその瞬間に、光が差し込む感じがして。
「デストロイヤー」もそうだし、すごいなと思って。延々と聴いていました。
石井:支え方が抜群なんだよね。
スリーピースの男軍団ブッチャーズに田渕さんが入ったことで、なにか無敵な世界になったんだよね。

石井:『生きてるものはいないのか』の音楽を田渕さんにお願いしたことで、そこから吉村君との友情もより深まっていきました。
そして、彼らから依頼が来たんです。だから、なんとかしたかったんだけど、全曲をフィーチャーしての映画ってね、非常に難しかった。
考え抜いて、これはできないと思ってしまったんだよね。
曲を生かさねばならないとしたら、どうしたらいいんだろうと悩んだんです。映画は映画の強い世界があるじゃない?
ドラマがあり、それを俳優さんたちが体現して行くというね。
その世界との融合は、無理だろうと。
ただ、音楽のライブという芯があって、それにドラマがくっつくというのは出来るかもしれないと思った。
ただ、それは、吉村君たちにとっては、本意じゃなかったかもしれないんだよね。
でも、「それでもいい」って、彼らは言ってくれたんだ。
「じゃあ、やろうか」ってことになった。そういうことで、僕が信頼している、一緒にやりたい俳優さんたちに声をかけたら「OK」ということだったので、やろうと思ったんだけどね。
準備万端整ってきて撮影2ヶ月半に、彼がね、突然、亡くなった。
その時点で、もうどうしていいかわからないという状態になってしまいました。
ほんとうに、まさかのことでした。予想がつかないことでした。しかも作品は始動していて、かなり深いことになっていたし、ブッチャーズの音を聴きこんでいたから。表面的に、趣味的に、いちロックファンとして聴くこととは、違う次元にいっていました。
オレの中で魂を震わせるものはなんだということです。それは「ソレダケ」という曲だったり、「アンニュイ」という曲ですね。そういう曲が芯になっていたんです。その時点で、まあ、彼は亡くなってしまったけど、なんとかしなきゃって思っていました。
でも、もう、自分ではどうにもならなくて、ちょうど『ネオ・ウルトラQ』で一緒に仕事をしてたから、いながき君に頼ろうと思って……。なんとかしてくれ!って。オレ、もう、なんにもその辺りの経緯を覚えてないんだよね、教えてくれる?

☆映画『ソレダケ』のシナリオの経緯
いながき:今、石井監督からお話いただいたことは、僕にお話をいただいた時点では、知らなかったことですよね。
僕が知っていることは、それ以降のことです。始めて僕に持ちかけていただいた時、監督からある資料をいただきました。それはとあるホームレスのカップルのインタビュー記事でした。30代くらいの男女のホームレスです。それを渡されて、こういう世界観で行きたいとおっしゃられてました。
石井:結構、調べたんだよね。
若いホームレスの話をやりたくて、なんでそう思ったか忘れたんだけど、多分、興味あったんだろうね。
劇映画で、ブッチャーズの音を使って、なにかやるんだったら、若い男女のホームレスの話をやりたいって思ったんです。これをなんとか、脚本に出来ないかと持ちかけたんですね。
いながき:このインタビュー資料に書かれてある内容が、抜群に面白かったんですね。
石井:ヤクザから逃げてる二人の話で、すごい、お互いもうどうしようもないバカな二人なんだけど、地獄のような状況を、二人で痴話喧嘩しながら乗り切っていく、切なくもバカたくましい人間力にとても惹かれたんだと思う。
いながき:そうですね。それが、今回のシナリオという意味ではルーツでした。しかも、ブッチャーズということで、僕は、90年代に青春時代を過ごし、ブッチャーズやナンバーガール、イースタンユースなど、ああいうジャパニーズオルタナって言っていいんでしょうか、とにかく、率先して聴いていた世代なわけです。
渋川:いながき君とオレ、同い年だっけ?
いながき:いえ、僕の方が三つほど下かと思います。
なので、見てきたものとしては、渋川さんよりも若干、下のものかもしれません。
ですので、僕はブッチャーズの方を向いていて、そして、ブッチャーズは石井さんの方を向いている、この構図があるわけです。そんな中、石井さんから声をかけていただいて、しかもど真ん中にブッチャーズがある企画ということで、なんというか、個人的には言語化できない感慨がありました。
そうして、石井監督から資料をいただいて、プロットを書き始めるんですが、どうにも、うまくいかないんです。僕が力不足過ぎて、石井監督に満足していただけないわけです。
今日、こうしてお二人と話すということで、当時、2013年夏からのメールでのやり取りを見直していたんですが、石井監督のイメージを全然僕が捉えきれてないんですね。5、6回、プロットを書きなおして、ようやく今ある形の原型になりました。
で、プロットを書き進めているある段階で、石井監督が、この映画は、「父と子の関係」、いわば「父性」ですよね、そういうものがテーマなんじゃないかとおっしゃったんですよ。その時点から、なんとなく、理解が出来始めたという感覚でした。

石井:オレ、自分も父親だけど、今、殺すべき親なんていないっていう実感があるんです。その若いホームレスたちの話を調べていると、徹底的に親がダメなんだよ。負の連鎖なんだよね。本当にそれが増えていて、負の連鎖を子供が背負わされていて、戸籍がなくなって、親がいなかったら、ほとんど犯罪に走るしかないわけね。その中で、美談になりうる人はテレビなんかで取り上げられてるけど、ほとんどそうじゃないからね。
男は、オレオレ詐欺へ、女の子は風俗へ、そういう世界が広がっていて、あまりにも厳しすぎる現実がある。けれど、それに直接的に、自分がなにかアクションを起こすというのは自分のスタイルじゃないし、映画的に濃くデフォルメして、なにか一つ、ブッチャーズの世界観と合体できないかと。
結構、それで、試行錯誤したんだよね。そんなやりとりがあって、その中で、面白いキャラクターが出てきたりしたんだけど、厳しい現実みたいなものをそのままやるというのも一つの映画のスタイルかもしれないけど、でも、今回のこの映画ではない。
いながき:そういう意味では、最終的には、テーマに収束させていくというよりは、キャラクターに収束させていくという作業の方が、条件面でも、一番初めに描きたかったことをうまくできるのかなという感じがあって、幸いなことに、渋川さんや村上さん、染谷さん、綾野さんという、僕の中ですでにイメージがある方たちに出ていただけるということで、僕は勝手に当て書きしてましたね。
与えられたシチュエーションで、キャラクター達が、何をしゃべり、どう動くかが、シナリオでは書けたので、それはよかったんですが、とにかく、そこまでの手さぐりが、困難でしたね。
石井:そうね。何がやりたいかということは見えてるんだけど、どう凝縮して、どう面白くするかっていうのが、結構難しかったです。最終的には、飛び道具的な現在の大胆な構成と世界観の導入を提案して、いながき君が懸命にまとめてくれた。
基本的には、僕といながき君は好きな世界が似てるんだよ。それが『ネオ・ウルトラQ』の時、わかったんだけど。この人のドラマ世界のデフォルメの仕方はオレと合ってると思った。でも、それだけに二人共リアリティをね、すっとばして暴走するところがある。

(次週は、石井監督の世界観とは、そして、映画における思想と暴力に迫ります。ますます深くなるお話、第三回をお楽しみに!)