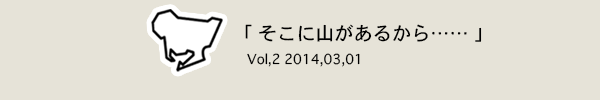(注:これは、まだ喫茶『マウンテン』が
いまほど有名になる前の話である)
中学も、高校も、大学も、母校の最寄駅は、
『杁中』という駅だった。
この杁中の文字が難読漢字だということで、
どうやら今は「いりなか」駅となっているらしいが、
どちらかというと、杁中駅の方が赴きがあって、好きである。
合計十年間、僕はこの杁中駅に通ったことになる。
中高大と同じ系列の学園で、中学と高校は男子校だった。
大学に入って急に共学になって、
しかも男女比で言えば圧倒的に女子の方が多く、
僕は途端に色めき立ったが、
とりあえず男子高マインドを全開で押し通した。
(と言っても、大学は途中で自主退学してしまうんだけど……)
杁中駅周辺というのは、瀟洒な建物が立ち並ぶ閑静な住宅街。
いわゆる山の手である。その山の手の中腹に、
かの有名な『マウンテン』はそびえたつ。
知らない人に一応喫茶『マウンテン』を説明しておこう。
まず、『マウンテン』はその名の通り喫茶店である。
だが別にコーヒーを楽しむような場所ではない。
主に料理を楽しむお店である。
ただ、ちょっとおかしな料理や尋常ではない量の料理を
楽しめる方でないと楽しめない。
メニューもおびただしい種類があるので、
どれがおかしな料理か、
どれがマシなメニューかわからない。
ついでに言うと、メニューの名前から
当たりか外れか容易に推測できない。
コスモスパやらヤングスパなど
訳のわからない名前が目白押しである。
ちなみに、コスモスパは土鍋で供される。
こんな調子の喫茶店だから、実は、中学生の僕らは
主に罰ゲームとして喫茶『マウンテン』を使用していた。
当時はまだ土曜日の半日授業が存在していて、
放課後は部室で夕方までだらだらするというのが定例だった。
授業が終わると部員みんなが集まって、
「昼飯なにする?」というのがだいたいの定跡。
だれかが『マウンテン』と言いだすと、
とりあえず大富豪かなんかやって、
部員それぞれを大富豪と大貧民と平民に分ける。
それから、部員は『山登り』を開始するわけだ。
席に就くと大富豪になったヤツが大貧民のメニューを決める。
だが、決められる前から大貧民のメシは大方決まっている。
大富豪は、大貧民のために『小倉抹茶スパ』を頼んでやる。
(正確には『甘口抹茶小倉スパ』らいしが、
部員は小倉抹茶スパと呼んでいた)
クサイメシならぬ、甘いメシである。
ほとんどの部員はこの『小倉抹茶スパ』が嫌いである。
だが、部の未来を背負うであろう人望の持ち主:マツダ君は
奇特な人物で、
この『小倉抹茶スパ』が大好物だった。
だから、このマツダ君が大貧民になると、しらける。
しらけるのを回避するには、
他のトンデモメニューを頼めばいいのだが、
部員たちは『小倉抹茶スパ』の相貌を確認したいがために、
やっぱり『小倉抹茶スパ』を頼む。
そしてマツダ君はそれを見事に平らげてしまうのだった。
時には、我々は『かき氷』というものも注文した。
これは登山中に出会う巨大な雪山のようなものだった。
しかもその雪山は、登山人数の割合に比例して標高が高くなる。
(つまり、同伴人数が多ければ多いほど、
店員さんが氷の量を増やすということ)
その時は、四人がかりの登山だったが、
我々の眼前に現れた雪山のいただきは、
天井からぶら下がるライトにひっつかんばかりにそびえていた。
雪山アタックの際には、常に雪崩に備えなければならない。
人数に応じて量が増やされるものの、
量に応じて受け皿を大きくするわけではないので、
一旦雪山が溶けだせば、
決壊し雪崩を起こしてしまうことは必至だ。
その前に一気に登頂せねばならない。
食速と融解との一騎打ちだ。
だがいつも我々は、敗北した。
雪崩に見舞われた机の上は氷とシロップと
アイスクリームの混ざったネチョネチョ液に侵され、
敗北感を胸に、下山を余儀なくされたのだった。
と、まあ、喫茶『マウンテン』を『山』に見立てて語るのが、
始めは楽しくて仕方なかったわけだが、
中学、高校と時が経つうちに、僕の『山登り』熱も冷めていった。
かなり出落ち感満載の店だから飽きるのも早いわけで、
僕は、土曜日の昼下がり、
部員の誰かが『マウンテン』と言いだしても、
「オレ、パス」を貫き通した。
カップ焼きそばのお湯を裏窓から捨てながら、
「いつまでも、山なんて登ってられないぜ」
とかなんとかキメ台詞を吐き、
みんなの『山登り』の背中を押しては、
その無事を祈る側に回ったわけだ。

やがて、大学に入学し、
『マウンテン』の存在も忘れかけていた頃である。
中高一貫校だったおかげで僕たちは、
ほぼ全員『マウンテン』がいかなる山か周知していたわけだが、
大学という場は、他府県からやってくる生徒も多い、
いわゆる『山登り』初級者ばかりだった。
そして、大学のクラスメートのアイザワ君は、
『山』の餌食になった。
ある日、教室に行くと、アイザワ君が浮かない顔をしている。
「イナガキ君、地元出身だよね」
「そうだけど」
「実は、喫茶店でバイトを始めたんだけど、ちょっと変なんだ。
地元出身のイナガキ君なら事情に詳しいと思って」
「ああ、マウンテン?」
僕は、『マウンテン』のあらましについて、
アイザワ君にレクチャーしてあげた。
僕の話を聞いて、アイザワ君は随分迷った挙句、
『マウンテン』のバイトを続けることを選んだ。
「せっかく選んでもらったんだし、バイト代も悪くないし、
それに店長も悪い人じゃないから……」
ちなみに、アイザワ君は長崎県出身の素朴で真面目で
親御さんからの仕送りを断り、
自分の稼いだお金だけで大学生活を送るという
模範的で愛すべきクラスメートだった。
そんなアイザワ君は、アルバイト店員として
毎週三日は『山登り』する猛者へと成長していった。
それ以来、僕は、アイザワ君にちょくちょく
『山』の情報を聞くようになった。
「アイザワ君、山の天気はどう?」
すると、アイザワ君は声を落として僕に耳打ちした。
「マウンテンって、かつてはカップル喫茶だったんだよ。
イナガキ君、これは君の心の中に留めておいてくれ」
女子の多い教室で、ためらいがちにそう言うと、
アイザワ君は顔を赤らめながら、その日も『山』へと向かった。
かわいいヤツだな、アイザワ君。
また、別の日、
「アイザワ君、最近の『山』はいかがですか?」
「イナガキ君、内部情報を漏洩するのは心苦しいんだけど、
『山』に来てもサボテンピラフには手を出さない方がいいよ」
「新メニュー?」
「試食させられたんだ。
駐車場に生えてるサボテン使えるなぁって店長がぼそっとね、
言うんだよ。
そしたら、収穫させられて、店長に渡すと、
サボテンピラフの出来上がりさ。
僕はバイトだからね、仕方なく食べたけどね、……苦いよ」
「教えてくれて、ありがとう、サボテンには手を出さないよ」
「うん、そうした方がいい」
今では名物メニューになっているらしい
サボテン系メニューの最初のいけにえはアイザワ君だった。
それ以降もアイザワ君とは時折『山』情報を交わしたのだが、
やがて僕が退学してしまったおかげで、
とんと『山』からは遠ざかってしまった。
今、再び、『山』に登りたいかと問われれば、
うーん、遠慮願いたいと答えるだろう。
僕はすでに『山』に登るにはロートルすぎる。
ただ、もう一度、訓練して、しかるべき時が来ればまた、
登山に向おうとも思う。
その時は、無事下山してこられることを祈っていてほしい。
(いながき きよたか)