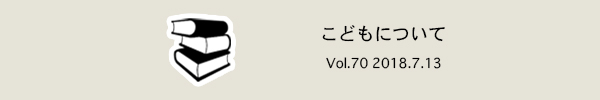昔、『ジュニア』という映画があった。アーノルド・シュワルツェネッガーとダニー・デビートのダブル主演である。
同じ主演キャスト二人で作られた『ツインズ』という映画が好評だったのか、監督もアイヴァン・ライトマン、主演も同じという布陣で作られた同作は、かすかな記憶を頼りに思い出してみてもさして重要な作品とは思えない。
しかし、忘れがたいものもあって、それは同作のテーマが『男性の妊娠』だったことだ。
一時期、我が家に子どもが生まれたころ、我が妻は、どうやら本気で僕に妊娠して欲しいと考えていたらしく、ネットであれこれ調べ、それがあながち不可能ではない、いや科学的には可能なのだと、力説していたことがある。
彼女は、(そして僕も)医学的なことに疎いばかりか、理系的なことはからっきしで、根っからの文系人だし、ソースはネット情報だし、眉唾この上ないのだが、まあ男性の妊娠を本気で考えるという辺りが文系っぽくていい感じだ。
妻が僕に妊娠を経験して欲しいと考えたように、実は僕もあながち妊娠経験をしたくないとも思わないでいる。人体実験のようなことをしなければならないならそれはそれでイヤだが、自然の営みの中で妊娠出産を経験できるのなら、ぜひともしてみたい。
と、こんなことを『男性』の僕が言おうものなら、この発言も誰かを傷つけてしまうのだろうかと、事後すぐに思いを巡らせなければならない時代ではある。が、経験してみたいと考えていることは本当である。
というのも、僕は常々男女ひとしなみにジェンダーから自由であればよいのにと考えているからで、仮に性差によらない妊娠が選択できるならば、ぜひとも男性だって妊娠すべきだと考えてしまうところがある。
先日、現実には堂々と表に出ているにもかかわらず、最も表に出してはいけないおじさんの代表格であるところの二階俊博さんが、またもやおもしろ発言を繰り出したというニュースを読んだ。
曰く「このごろ子どもを産まない方が幸せじゃないかという勝手なことを考えて」いる人がいるのだそうだ。「皆が幸せになるためには子どもをたくさん産んで、国も栄えていく」のだそうだ。
まあ彼は、まさに「このごろ子どもを産まない方が幸せじゃないかという勝手なことを考えて」いる人がいるのだというような勝手な考えを抱いているわけなのだが……。
一つ、言っておかなきゃいけないのかなと思うことがある。
それは、僕の家は子どもが一人いて、それは勝手にうちがそうしただけで、皆が幸せになるために、いわんや断じて国が栄えるために、うちの子どもはいるわけではないということだ。「どうだ、子どもを産んだにもかかわらず、やけに勝手な考えを抱いている家族がここにいるぞ」などと、訳もなく主張したい気分になってしまうのである。
どうしてこんなことを言わなきゃいけないと感じなきゃいけないかというと、まさにこの表に出しちゃいけないおじさんの発言のために、こんな表明でもしなければ、裏返って、子どもを持っていること自体に後ろめたさを感じなければならないような気にさせられてしまうからだ。
このおじさんの理屈に従えば、子どもを持たない人々は国の繁栄を考えない「非国民」であり、逆に子どもを持つ僕は「国民」であるという理屈になる。
いやいや、子どもを持っただけで、否応なく「国民」の仲間入りさせられてはたまったものではない。僕はごめんだ。
とにかく、僕はこういうおじさんの理屈の内部で生きるくらいなら、「非国民」という外部に居続けたい。
こんな感じで、あくまで表に出してはいけないおじさんの理屈を全否定しなければ、本当にしたい話ができないというイヤーな時代に僕は生きているわけだが、僕は本当は子どもといる時間を祝福したい気持ちをことあるごとに抱いているのだ。
僕には子どもを持たない未来も大いにあった。きっとそれはそれで幸せな未来であったに違いない。
けれど今僕には子どもを持つ未来が連なっている。この現実は、僕にとても多くのことを考えさせる。
毎週末、うちの子どもは公園に連れて行けと僕にせがむ。
近くの『たこさん公園』の週末の顔ぶれはいつも決まっている。
あゆみちゃんやあおいくん、ゆうたくん、その他入れ替わりのゲストたちで週末の『たこさん公園』には子どもが一杯だ。
彼らは一緒にサッカーをしてほしいと節操なく僕にせがむ。調子がよければ率先してサッカーをするし、疲れていたりすると、あれこれ言い訳して拒む。拒むと、「えー」と非難の目を向けられる。
ちなみに僕はサッカーがものすごく下手で、小学生相手くらいがちょうどいい、というかむしろ彼らの方がうまいくらいなので、うまく釣り合いがとれている。
うちの息子は好き勝手に遊んでいる。
僕は年長者達とサッカーだ。
一段落して、たこ滑り台の脇に腰をおろし、ふと考えた。
ああ、そうか、息子がいなければ、今ここに僕はいないのだ、と気づいたのだ。
別にとりたててフォーカスするほどのことでもないが、息子がいなければ、あゆみちゃんやあおいくんやゆうたくんと話すことはなかったのだ。そんな風に意識すると、この出会いは息子がもたらしたものだという事実が揺るがせられないものだなと得心する。
それに、僕は二週間に一度息子と図書館に行くことになっている。
もっぱら息子が読むための本を借りるのだ。
この間、息子が「名作が読みたい」と言い出した。
なんでも、彼の中では「桃太郎って名作だよね?」らしく、僕の名作観とは大分ちがっているのだが、まあ、そんなことはいいとして、僕は背表紙に名作シリーズと書いてある本の棚を見つけ、息子を呼んだ。
彼が手に取ったのは「ガリヴァー旅行記」だった。
もちろん、スウィフトの純粋な翻訳ではなく、児童用に翻案されてはいるが、開いてみるとなかなかのボリューム、「ま、こつこつ読み聞かせるか」と思い、借りてみた。
考えてみれば、僕はスウィフトを読んだことがない。それこそ、子どもの頃、名作シリーズの手合いの『ガリヴァー旅行記』を読んだだけだ。記憶も薄れている。
帰宅して、就寝前、シコシコとガリヴァー旅行記を読み聞かせていると、内心、「はぇー、こんなんだったっけか」と驚く。
ガリヴァーが小人の国リリパット国に迷い込んだことは覚えているが、その国が、隣国ブレフスキュ国と戦争していて、その原因が卵の割り方というくだらない理由だったなんて、僕は多分、息子がいなければいまごろ思い出してもいなかっただろう。ここにも息子によって誘導されている自分を発見する。
世の中には、子どもを、まさに『感性の王』として見る向きもあるようだ。無垢な彼らの発想や表現は真に芸術的なものだとむやみに称揚するような風潮のことである。
僕は、そういう風潮に実は眉をひそめる。
というか、そういう風潮こそが、子どもを大人の鋳型に押し込めているとさえ感じる。
子どもは、僕が直接触れて感じるところによると、徹底的に不条理で不気味な生き物だ。
彼らは大人の外部に存在している。
僕が子どもに関して思い出すのは、『カラマーゾフの兄弟』におけるイリューシャとコーリャ・クラソートキンだ。もっと言えば、彼らを巡るジューチカとペレズヴォンという犬だ。
イリューシャは、スメルジャコフにそそのかされ、針を忍ばせたパンをジューチカに食べさせる。それを飲み込んだせいでジューチカは生死不明となる。この事実をイリューシャはコーリャに打ち明ける。コーリャは叱責し、絶交を匂わせる。が、後に病床に就くイリューシャの元にコーリャはペレズヴォンという犬を届ける。イリューシャはペレズヴォンを見た途端、ジューチカだと悟り、歓喜に包まれる。
僕は一連の流れを読み、戦慄するのだ。これこそ児童だと。
一方、柄谷行人は「子どもは大人の奴隷ではない、大人が子どもの奴隷なのだ」と書いた。
僕は学生のころ、頭では理解していたつもりだったが、いまいち得心しなかった。が、息子によってあゆみちゃんやあおいくんやゆうたくんに導かれ、『ガリヴァー旅行記』に導かれる今の僕にとって、その言説は真に迫る。
そして大人を使役する子どもは、イリューシャやコーリャのようにとても不気味である。そんな不気味な存在を身近に置くことは、逆説的に生き方を豊かにすると、僕は実感する。
もう一度、表に出してはいけないおじさんの話に戻ると、あの二階さんというのは、やはりもう一度、自分の言った「子ども」ということについて深く洞察すべきだ。
子どもを産むのが男でも女でも僕はかまいやしない。子どもを産むということはどういうことなのかが問題なのではなく、いつでも、子どもとはなにかが問題になるのだと僕は考えている。
(いながき きよたか)