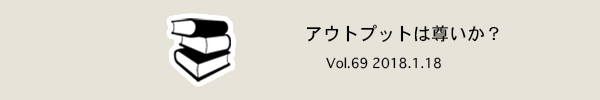先日、国立近代美術館で熊谷守一を観た。
ちょうどその日岡﨑乾二郎氏の講演があるということで楽しみに出かけていった。
まず絵を観た。ほぼ年代順に網羅してある大量の展示だった。
熊谷守一の絵は、いわゆる晩年になればなるほど、一枚だけ取り出して見ても、それはどうも安直なものに感じられやすい。
例えば、まさに僕がその通りに思っていたわけだが、講演の冒頭で岡﨑氏が言った通り、熊谷守一の絵は、およそ百貨店などで開かれる類いのあからさまに文化村などが好きな女性に向けられた作家たちの展覧会で飾られるような絵とほぼ変わらないという印象を持たれてしまうかも知れない。
けれど、展覧会をぐるりと周り守一の絵を直に観て、さらに岡﨑氏のレクチャーで理解を深めてみると、守一の絵画が深い教養の末に成り立っていることがわかる。安直にただ感覚に訴えるだけのものではないことがわかる。ただの「猫がかわいい」というほどの感想では捕らえきれない考察の末に成り立っていることがわかる。
その理解がどんなものか、それは展覧会に行って絵をみて、文献を読み、さらに自分よりも深く理解している人間の話を聞く機会を設けてみるほかない。
もしかしたら守一の絵はセンスがいいと語られるかも知れない。けれど、そのセンスの良さのようなものにはひとまずなんら興味がわかない。このような言説は思考停止のスイッチのようなものだからだ。それよりも興味を向けるべきは『この絵』が一体どんなものなのかという問いにある。
いずれにしろ音楽にしろ絵画にしろ、文学にしろ、『センス』や『直感』というおよそ中身のない言葉で計られ尊ばれてしまう類いの作品にはまったくもって興味がない。いや作品には罪はない。それはすべて受け手の問題だ、受け手に知性が足りないばかりに、無意味で華美なだけの言葉で語られてしまう作品についての言説にはさらに興味がない。
守一は長生きだった。97歳まで生きた。
画業を振り返ると、若い頃にもよい絵を描きはしたが、40歳過ぎるまでのらりくらりしていたようだ。他の画家とは違い、戦争中もおそろしく寡作であった。プロパガンダ絵画も残しているが、見ようによれば焼け野原に巨大な鳥居がズドンと残っているだけという、かなり皮肉めいた、反戦や厭戦という思想を超えたよくわからない絵だった。
守一の絵が急激に展開し始めるのは戦争の時代が終わった後、60代も過ぎたころと言っても過言ではない。
にも関わらず、それまでの画風の変遷も含め、生涯守一の絵画は展開し続ける。あるモチ
ーフを見つけると、(そしてそれが評価されると)大いにそこに止まる画家が多い中、守一の絵画の変遷は極めてまれなのではないか。
守一はある明確な意図をもっていたことによって、画風が変化していく。時にはまったく絵筆をとらずにいた時期も挟んだ末にだ。
この事実に触れて、僕は少なからずはっとした。
世に早熟な天才はもてはやされる。若ければそれだけで才能だと思われないこともない。
そして、世の風潮もとにかくインプットよりはまずアウトプット、内省よりは表現へというベクトルを強調する、それを尊ぶ。
しかし、はたしてそれはよい結果をもたらすか、疑問に思うことが多い。
守一は絵筆をとらない間、研究をし、確かな理論を構築していった。その理論を絵画で表現した結果が今残る彼の絵画に結実している。
衝動で残された作品もそれはそれで尊い、しかし、場当たり的な、人気を目的とした作品などは、たしかな教養に裏打ちされた作品の前では無いものに等しい。理由は簡単だ。鑑賞に耐えないからだ。
これには自省するほかない。僕も大いに場当たり的に文章を書いている。人気に結びつかないところがなお質が悪い。
強調したいことは、ようは何かを発見した末に作品は残されるべきだということだ。
守一は二枚、ショッキングな絵を残している。ショッキングだが、二枚とも決して露悪をもくろんだ絵ではない。
その一枚に『陽が死んだ日』という絵がある。幼いまま死んだ次男の亡骸が描かれている。この絵はほぼ未完成のままサインが施され完成をみている。なぜなら、途中で自分が息子の死を描いているという事実に気づき、描くのをやめたからだ。より正確に言えば描けなくなった。
メロドラマ風に言えば、息子の死を前に悼むより先に絵を描いてしまう芸術家の性の無情さに気づき愕然としたなどと、それこそ芥川の地獄変のように、語られてしまうかもしれない。
しかし、事の次第はどうやらそうではない。
画業をひもとけば、守一はしばしばいわゆる捧げる絵を描いている。岸田劉生が死ぬと『道路と土手と道』にうり二つの構図の絵を描いたりする。美学校時代の教師であっただろう黒田清輝の絵を再解釈したような絵も残している。
まるで絵を描くことでなにかが再生すると考えているようだとも思える。
もしかしたらそのような感覚のまま、息子の死に際し絵筆をとったのではないか。メロドラマ的ななにかではなく、単に絵画に対する理解が自然とそうさせたのではないか。
おこがましさを承知であえて言えば、この感覚はとてもよくわかる。
描くこと/書くことそのものは、再生の成分を多かれ少なかれ含んでいる。
作家はひょっとするととある作家のとある作品を脱構築することはできるかもしれない。しかし、死せる人間を再生せしめることはできない。ただキャンバスに写し取ることができるだけだ。
おそらく守一はそのことに気づき、愕然としたのではないか。
『陽の死んだ日』の筆致は生々しい。色をゆるがせにしない守一の絵の中で異質だ。キャンバスの地はところどころむき出しで、守一が初期にこだわったろうそくが描かれてはいるが、燭台を示すだろう円筒形の何物かは輪郭を残すのみでかすれてしまっている。
今、国立近代美術館に行くとその様子を直に見ることができる。
(いながき きよたか)