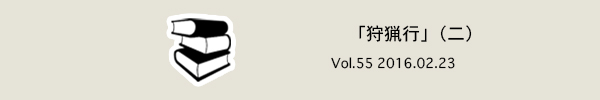尾根の中腹に腰を下ろし、青空を見ていた。
セコ役の初老は木立に降りて行ったまま姿が見えない。時折、野鳥の鳴き声が聞こえるばかりで、鹿の気配すら感じられない。
やがて借りていた無線があわただしくなる。見学者への好意でセコとタツの間で交信される会話が聞こえるようにしてもらっているのだ。
が、それを聞いても僕には詳細な状況がつかめない。ただ、どうやら猟犬が鹿を捕らえ、備えているいずれかのタツの方へと追い立てているという。
「行ったぞ!」
「了解……」
その後、無線は再び静寂となる。
固唾を飲む、というより、これから何が起こるか僕はわからないでいる。煙草に火をつけたりして、呑気なものである。
ドーン……。
やまびこを聞いたことがなかった。
映像の中では聞いたことがあったかもしれないが、空気の振動を直に鼓膜でとらえたことはなかった。そして銃声ならなおさらだ。
さきほどの炸裂音は確かに銃声だった。
不意に、僕は文字通り驚いた。びくっと身体が震えた。
そしてまた無線がにぎやかになる。
『はぐったか』
その地方では、獲物を外したことをそう言うらしい。
再び、山中全体に銃声がこだまする。
何度かの格闘の後、我々はついに二頭の鹿を『転ばした』のだった。
しかし、その姿はまだ見えない。
まだ正午を回っていなかった。最近、見学者を同伴すると獲物にありつけない日が続いたという。それでなくとも、普段なら一回戦、二回戦と長い時は六時間にも及ぶのだそうだ。タツが二時間息をひそめ続けることもざらだという。
が、こういう日もある。猟師たちの表情は幾分軽やかに見えた。
獲物を山から降ろしにかかる。我々見学者は獲物が転がっている場所へと山を下りた。
オレンジ色のハンティングベストが木立の隙間に見えた。獲物はあそこにいるのかとわかると歩が早まる。日差しはあるが足元はところどころ凍っている。滑らぬように沢近くまで降りた。
民家らしき小屋のすぐ近くに鹿は横たわっていた。まだ息がある。口元から時折弱々しく白い息が漏れている。
僕たちは飢えていない。言う人が言えば、無益な殺生かもしれない。多分そうだろう。そのことに反論の余地もない。
けれど、この猟がただ官能的なだけのスポーツかと言えば決してそうではない。
いうなれば、生きる営みの真似事だ。
僕は、休日を使って、猟師に従い山を分け入って、獲物追い詰め捕獲した。ある種の困難さを進んで体験することでしか、生きる営みに自ら直に触れることができない、それは必要のないことか、目の前で死に行く牡鹿を見つめながら、自問は尽きない。
僕たちは数人で二頭の鹿を運んだ。
僕は雄々しい角を持った。持つ手にかすかに残る生を感じる。運びながら弱々しい力が時折伝わった。
深い黒を宿した鹿の瞳は息絶えると水晶のように透き通る。まるで命が瞳から抜け落ちるように。猟師はそのことを僕に教えてくれた。彼らも不思議だという。猥雑さと野蛮さの中にあって、神聖さが同居しているような感じがする。
猟師小屋に戻り、獲物を解体する。食べるためである。
鹿の身体を水で洗い流し、猟師は慣れた手つきでナイフを操る。腹を裂き、臓腑があふれる。僕もそれを手伝う。前足を持ち、仰向けの鹿を倒れないように抑える。足元に血が流れる。体内を洗い流す山の冷水がかけられると、やがて湯気が上気した。僕は鹿の内部に触れた。一瞬ためらわれたが、そうしなければならないように自然と手が出た。今まで感じたことのない温もりだった。それは優しさに紐づかない温もりで、僕は無暗に感謝した。
猟師が心臓を探していた。解体役の猟師が心臓を手にするとセコ役の猟師がやってきて、先端を小さく丸く切り取る。ふとそれまで和やかだった雰囲気がそこだけ厳かさのような空気をまとった。彼は切り取った心臓の端にナイフで十字の切れ込みを入れると、沢の入口に立って頭を垂れた。沢の向こうは遠く山並みが続いている。そちらに向かって心臓の端を捧げた。
女性猟師の一人が何か聞きたげな僕に「山の神様に感謝するの」と教えた。
ふと先ほど来の自問が少しだけ解けた気がした。
僕たちが猟をするというのは、まったくの無益ではなく、わずかな有益さがあるという確信が拡がった。
それに罪のようなものに決して無頓着なのではないのだ。それはあり、犯さざるを得ない存在はハレとケを往復する。それですべてが救われているわけではないが、すべてが罪深いというわけでもない。
ますます揺らぎのなくなる今の時代には、殊更、この罪と救いの往復という浮遊感がもしかしたら必要なのではないか。
鹿の解体を終え、僕たちは過日捕らえたという猪の解体に取り掛かった。
動物を食すまでには、実に手間がかかっている。手間を惜しむと、食べるための猟は無駄になる。
猟師と見学者問わず、みんなで一緒に、食事ために、手を動かし、準備をする。
実はこれは猟そのものに勝るとも劣らない特別な体験となった。生きる営みに直結する共同作業がここにもあった。
やがて山に陽がかげる頃、準備が終わり、宴となった。山小屋に入り、手間をかけ猟師が僕たちのために作ってくれた料理を囲んだ。
酒を呑み交わし、放談し、時間を共有した人間たちと肉を食う。僕はこれほどの享楽を久しく味わわなかった。本当に幸せな時間だった。
絆やふれあいという言葉に警戒心がある。
それらは優しい顔をして近づいきて、僕らの寝首を掻く。生きる感覚を麻痺させる。
しかし、それは言葉が悪いわけではない。使う人間の意識が悪い。
絆やふれあいは人間同士が何かを共有している時に生まれるだろう。
それが罪だけならば、やがてよそ者をあしざまに排除するだろう。しかし、罪とともに他者の必要性、享楽、悲哀、それらを包摂した多様さを共有した時、ふれあいはとても人間を癒す。
僕は今回の狩猟行で猟師たち、見学者たち、そして野生の鹿とふれあえた、それは罪だけを共有したふれあいではなかったのだ。
最後に、今回お世話になった猟師さんたちには、惜しみない歓待をいただきました。やはり圧倒的な贈与は人間を救うということを身をもって体験しました。本当にありがとうございました。
(いながき きよたか)