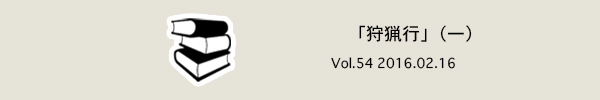ここ数年、ある考えに憑かれている。憑かれるなんていうとおおげさである。であるが、まあ自分にしてはけっこう固執している方かなと思う。
その考えとは野生の動物を狩ることについてである。
山に入り、武器を携え、野生の動物を見つけ出し、倒し、山を下り、解体して、食す。
この一連の流れを何度も夢想している。
なぜこんな考えに憑かれたか、よくわからない。
ただいくつかの契機はあった。
今ではどうかわからないが、考えてみると、僕の子供の頃は、結構文明論的言説があふれていたように思う。ちょうどバブル期だったからか、『戦後』の末期だったからか、ちょっとわからないが、とにかく極限を迎えた文明の真っただ中にいるからこそのそのものへの危機感を煽るような言説にたびたび接させられたものだ。
例えば、「はだしのゲン」は必ず読ませられたし、「ヒロシマノート」や「風がふくとき」などの核シンドロームものも推薦図書に必ず上がっていた。「風の谷のナウシカ」はさることながら、同時期に公開された「少年ケニア」にはかなりのトラウマを植え付けられたものだ。
これらは「戦争反対」や「エコロジー」を訴えているはずのところ、少年だった僕は逆に文明亡きあとこそいかに生きながらえるのかばかりに思いが寄った。
そんなわけで少年の僕は一番近い文明の危機、戦争について知りたがった。運よく戦中派はまだまだ健在だった。両祖父の戦時中の足跡をねほりはほり聞きたがった。
彼らの話を念入りに採取した結果、感じたことは単純なことだった。生きることは、おそらく食べることであるということだった。
別に戦争は人間同士の殺し合いに尽きない。人間の大方のカロリーが戦争に奪われるため、生活は著しく困窮する。戦争で生き残れる者は食べられる者だけ、これが両祖父の話の教訓だ。
母方の祖父は徴兵検査丙種にて内地の食糧倉庫番となったらしい。それが生き延びる由縁となった。
父方の祖父は入満し開墾に従事した。極寒の地で作物を得ることは困難を極め、現地中国人・朝鮮族たちになにかと教えを乞ったという。終戦後はシベリア抑留、そこで生きながらえたのは、運よく配膳係を任命されたためだ。
生きることは食べること、極限状態ではいかに食物の近くで生きるかが生死の分け目となる証左だ。
(同時に思いだすことがある。吉本隆明さんは高度文明社会の裂け目にあるような貧困状態を指して、「死ぬな、盗め」と言った。餓死してはならない、餓死するくらいなら盗めと。両祖父の戦争エピソードをちょうど逆向きから見るとこのような言葉になるだろう)
残念なことに、というと不謹慎か、けれど、まあ、目線を変えれば残念なことかもしれない、それは、今、僕は手を伸ばせば食い物がある環境に生きているということだ。
これはいちおう幸せだ。死にはしない。
ただなんとなく自分の中の生の感覚が鈍っていくような気分に陥る。
例えば、変な話だが、執筆時幾日か風呂に入れずにいる時など自分が清潔な時には気付かなかった深奥に眠っている野蛮に無暗に気付かされる気がする。つまり清潔さは、あるいは漂白と言ってもいい、そういうものは真の人間らしさを少しだけ奪う。
奪われている時は気付かないが、そして気付く必要もないが、しかしふと好物のハンバーガーなどを食っている時、方や自分の野生はどうなのだと確かに直感するのだ。
もしかしたら、高度文明に嬉々として浴しながら、同時に自分はある種の困難さ、それを野生と言ってもいいかもしれないが、文明ではないものを求めているのかもしれない。と、そう思い当たった途端、ムズムズしてきたのだ。
そういうわけで、機会を得て、先週末狩猟見学に行ってきた。
もちろん銃は持てない。日本社会において銃を持つには相当の手続きが必要になる。それを待たずにひとまず狩猟に同行することにしたのだ。
日本では猟期が定められている。意図としては野生動物保護だろう。これについて様々意見はあろうが、ともかく、二月は十一月に始まった猟期の最後の月である。
ご存知の通りこのところ寒さが続いている。当日も寒さが危惧されたが、思いがけず和らいだ。
早朝集合場所にて、僕は緊張していた。
その猟は巻き狩りといって数人のチームによって行われる。
構成は地元の猟師たち、それに加えて都内の有志たち、総勢十人ほど。
めったなことがない限り進んで見知らぬ人間たちの間に加わることなどしないので、うまくコミュニケーションが図れるか不安だったが、おそらく見てやろうという興味が勝ったのだろう、照れ屋にしては輪に食い込んだように思う。
巻き狩りは、セコ(勢子)とタツ(立)という役割に別れる。
セコは獲物を追い立てる役、タツは射手だ。
狩りの朝、あらかじめ足跡を探り獲物の当たりをつけたエリアにタツを配置する。その中央から勢子が猟犬と共に獲物を見つけタツに指示を送る。
その日の作戦を終え、いざ狩りが始まる。見学者は当然作戦の埒外に置かれざるを得ない。ただ数人、尾根の中腹までセコの後をついていいことになった。僕は立候補し、二匹いる猟犬の一方ランの鎖を持たせてもらうという幸運にもありついた。もう一方の猟犬チビを引き連れたセコは、初老ながら尾根の道なき崖をするすると降りていく。後をついていくのも一苦労で、ようやくセコに追いつくと、そこで犬を放すという。自動追尾させ、セコがその様子を伺いつつ獲物を見つけ出すのだ。ランとチビは鎖を解かれると崖を駆け下りていった。セコもするすると後を追っていく。
あとは静かなものである。尾根の中腹に残された僕の眼前には冬枯れた木々と遠い青空、時折野鳥の鳴き声が聞こえるばかり、これが狩りだと知らなければ、ただの森林浴である。
(以下、次週)
(いながき きよたか)